始皇帝につかえた丞相「呂不韋」の最期と、名言「奇貨居くべし」の意味を、わかりやすく解説いたします。
呂不韋は、始皇帝の母「太后」との密会で罪に問われ、謹慎。その後、流罪となった。
絶望した呂不韋は服毒自殺・・。しかし本当は始皇帝に暗殺されたのではないだろうか。
「奇貨居くべし」とは、「良い品物・掘り出し物を発見したぞ」という意味。
しかしその本当の意味は、あまりにも「私利私欲」にまみれたものであり、後の呂不韋の破滅を暗示していた。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
拙者は当サイトを運営している「元・落武者」と申す者・・・。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
- 呂不韋は、「始皇帝」に流罪にされたことで絶望し、毒を飲んで自殺したことになっている。しかし実際には「始皇帝」に暗殺されたのではないか
- 「奇貨居くべし」とは「掘り出し物を見つけた」という意味だが、立派な意味ではなく、呂不韋の「私利私欲」でしかなかった。
- 始皇帝は、呂不韋の息子ではないか?という疑惑だが、考察してみた結果、その可能性は極めて低い。
呂不韋の最期が壮絶!服毒自殺ではなく、実は殺された?
秦の始皇帝につかえた丞相(大臣)「呂不韋(りょふい)」。
その最期は、壮絶。そして悲惨なものでした。
呂不韋は、始皇帝の母「太后」と愛人関係にありました。
そして、太后のもう1人の愛人「ろうあい」が反乱を起こしたことにより、「呂不韋」も連座して謹慎処分となります。
呂不韋が幽閉されても、始皇帝は絶大な力を持つ「呂不韋」が反乱を起こすことを警戒していました。
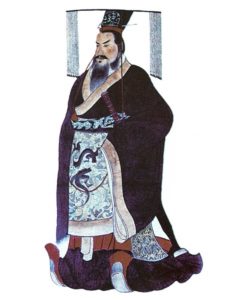
≪始皇帝≫
「引用元ウィキペディアより」
紀元前236年、始皇帝は自宅謹慎していた「呂不韋」を、「蜀」という山の中にある僻地へと幽閉します。
紀元前235年、絶望した呂不韋は毒を飲んで自殺した・・・・と言われています。
しかし、呂不韋は本当に自殺なのでしょうか?
個人的には、密かに始皇帝が放った暗殺者に暗殺されたのではないかと思います。
呂不韋の実力と名声は、当時からかなり際立っていました。
生かしておいては、必ず後の害になるでしょう。
もし万が一、敵国に呂不韋を奪われでもしたら、「秦」の情報は全て筒抜けになります。
とはいえ、大きな功績を残し、太后との密会の証拠もない「呂不韋」を、堂々と処刑するわけにもいきません。
やはり始皇帝は、呂不韋を暗殺したのではないでしょうか。
もしくは、始皇帝の側近が「そんたく」して、独断で呂不韋を暗殺したのかもしれません。
奇貨居くべし!歴史に残った名言と「奇跡」の出世物語
「奇貨居くべし(きかおくべし)」。
今も残る、呂不韋を代表する名言です。
この言葉は、まだ趙国の首都「邯鄲(かんたん)」で、呂不韋が商人をしていたある日、彼が口にした言葉です。
意味を現代語訳すると「掘り出し物を見つけたぞ」という意味。
呂不韋が掘り出し物と言ったのは、邯鄲に人質として住んでいた「秦」の国王「昭襄王(昭王)」の孫「異人(のちの荘襄王)」を発見したときです。
呂不韋はこのとき、「異人」を秦国の王にするために、巨額の投資と裏工作を開始したのです。
奇跡的にも、この「裏工作」は大成功。
「異人(この頃「子楚」と改名)」は、秦国の「王」の座を手に入れ、「王」となるのです。
この功績により、呂不韋は最強国「秦」のNo.2「丞相」という位を手に入れます。
「奇貨居くべし」・・・掘り出し物を見つけたぞ、という意味ですが・・。
これはあくまでも「投資すべき良い者を見つけた」という意味であり、「金のなる木を見つけた」という意味でもあったかもしれません。
呂不韋の目的は、あくまでも「自分の利益」。人のことなど考えていません。
ましてや、その時まだ生まれていない「嬴政(えいせい)」のことなど、考えてもいないはずです。
「奇貨居くべし」
この言葉の真の意味は、「いい獲物を見つけた」という意味。つまりそこには「私利私欲」しかなかったのです。
その証拠に、呂不韋は「荘襄王」の息子「始皇帝」を、自分の良いように利用しています。
それが原因で、呂不韋は悲惨な最期を遂げることとなります。
「奇貨居くべし」・・・この言葉は、呂不韋の後の「破滅」を暗示していると言えるのではないでしょうか。
呂不韋は「始皇帝」の父親?本当のところを考察してみた
始皇帝には、一つの疑惑がありました。
「始皇帝・嬴政は、荘襄王の息子ではなく、実は呂不韋の子ではないか?」
という疑惑です。
こんな疑惑が浮上したのには理由がありました。
嬴政を産んだ母親「趙姫(太后)」は、もともと呂不韋の愛人でした。
美しい趙姫に一目惚れした「荘襄王」は、彼女を自分に譲ってくれるように呂不韋に頼んだのです。
その後、趙姫は「嬴政」を出産。
ある歴史書には
「趙姫が荘襄王に譲り渡されてから、嬴政が誕生するまで、10ヶ月以上の期間があいている」
と記されています。
この歴史書が本当なら、始皇帝・嬴政は、「荘襄王」の子で間違いありません。
しかし、「疑惑」が完全に晴れたわけではありません。
もしも「始皇帝」が「呂不韋」の子であるなら、『紀元前778年』からこの時まで『500年以上』も続く「秦」の国の「正統性」が崩れることとなります。
疑惑は本当なのか?始皇帝の実の父は、「荘襄王」「呂不韋」いったいどちらなのでしょうか?
有名な映画「始皇帝暗殺」では、「呂不韋が始皇帝の実の父」という説を採用していましたが・・・。
考察してみましょう
結論を言いますと「始皇帝が呂不韋の子であるはずがない」と思います。
理由は簡単。
もしも「始皇帝が呂不韋の子であるなら、荘襄王が始皇帝・嬴政を自分の後継者にするはずがない」から。
荘襄王には、始皇帝・嬴政のほかにも「成蟜(せいきょう)」など何人かの子がいました。
始皇帝・嬴政が、荘襄王の息子かどうか、本当のところを知っていたのは「呂不韋」「趙姫」の二人だけです。
もしかしたら、趙姫が荘襄王にゆずられた後も、呂不韋は趙姫と密会していたかもしれません。
もしも「呂不韋から趙姫をゆずられてから10ヶ月未満で始皇帝が誕生」していたら、荘襄王が気が付かないはずがありません。
また「趙姫」と「呂不韋」が、荘襄王にゆずられた後も密会している可能性は、とても低い気がするのです。
なぜなら呂不韋にとって、「趙姫」をゆずった頃は、人生で最も大切な「荘襄王を王位につける」という大仕事をしていた頃なのですから。
もしも密会していたとしても、荘襄王は何も気が付かなかったのでしょうか?
荘襄王はおそらく、嬴政が自分の子であるという確信があったのでしょう。
だからこそ、荘襄王は自分の後継者として「嬴政」を指名したのだと考えられます。そして「呂不韋」をその補佐役にしたのでしょう。
王様が、実は先王の子ではない。こういう逸話は、いくつもあります。
始皇帝と同じ時代に生きた楚の「春申君」。
織田信長の義父「斎藤道三」と息子「斎藤義龍」。
「豊臣秀吉」と「豊臣秀頼」。
始皇帝の正統性をおとしめて、国を乗っ取ろうとする者たちによる、いわゆる「プロパガンダ(政治宣伝)」ですね。
「始皇帝」の場合、「呂不韋の子」であるという説の信憑性は、とぼしいと考えられます。
『呂不韋』について「ひとこと」言いたい!
呂不韋・・・・。あまりにも欲を出しすぎたことが、その破滅を招いたと言えると思います。
もともと、呂不韋には、それほどの野心があったとは思えません。
人気マンガ「キングダム」では
「嬴政を排除して、自分が秦国の王になろうとしている」
という設定になっています。
確かに、呂不韋は「始皇帝」を「あやつり人形」にして、秦国の権力を自分とその子孫に集中しようとしていた節があります。
しかし、自分が王になろうとしたは、低いと思うのです。そもそも正統性が保てないと思います。
呂不韋の失敗は、「始皇帝」の母親である「趙姫」と密会してしまったこと。
今で言う「スキャンダル」が出てしまったこと。それが唯一の失敗でした。
もしも呂不韋が本気で「始皇帝」を補佐し、天下統一に成功していたら、どうなっていたでしょう。
「呂不韋」は、「伊尹(いいん)」「太公望」「管仲」「蕭何(しょうか)」「諸葛亮孔明」のような、「名宰相」たちと肩を並べるほど、歴史に名を刻んでいたはずです。
スキャンダルで名声を失った・・・。
詰めが甘いとしか言えないですね。
もしも「奇貨居くべし」という「私利私欲」の精神ではなく、「嬴政を史上最高の名君に押し上げる」という大きな志があったら・・・。
呂不韋は今頃「英雄」として扱われていたかもしれません。
大歴史家「司馬遷」は、私利私欲に負けて命を落とした宰相「春申君」に対して
「春申君老いたり」
という激烈な言葉で批判しています。
「呂不韋老いたり」とはいえません。
なぜなら「荘襄王」に投資をはじめたときから、彼の目的は「志」ではなく「私利私欲」だったのですから。
「呂不韋」は「春申君」以下だった。残念ながら呂不韋の評価は、これが打倒な気がします。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 呂不韋は、始皇帝に流罪とされて絶望し、毒を飲んで自殺した。と言われているが、実際には始皇帝に暗殺されたのではないだろうか
- 「奇貨居くべし」とは、「掘り出し物を発見したぞ」という意味だが、それはあまりにも「私利私欲」にまみれたものだった。
- 始皇帝は呂不韋の息子では?という説があるが、その可能性は極めて低いだろう。
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
「キングダム」関連記事
以下のリンク記事でも、「キングダム」の「人物」「逸話」などについて簡単に理解できるように、わかりやすく解説させていただいております。
よろしければ、こちらの記事も、ぜひお役立てくださいませ。
リンク記事は別タブで開きます。
「秦の武将・軍師たち」関連記事
「王翦・王賁」
「昭王・六大将軍」
「秦の始皇帝」
「呂不韋」関連記事
「趙・三大天」
「戦国四君」
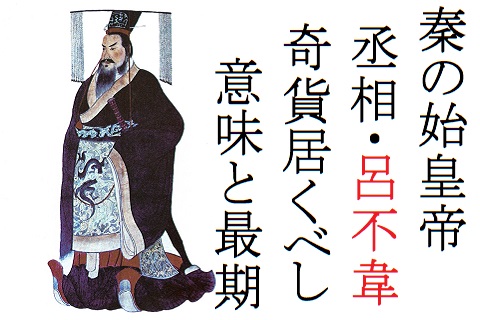

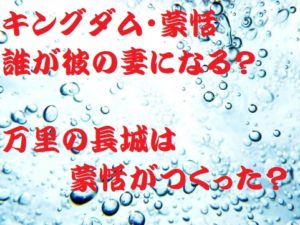
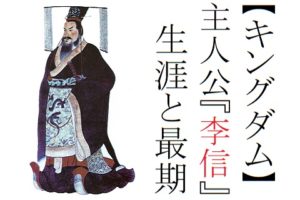
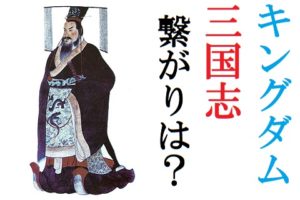
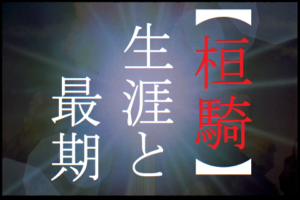

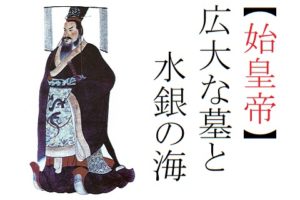
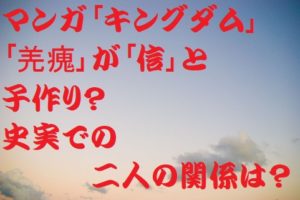
コメント