朝廷とは何なのか、この記事を読めばカンタンに理解できるよう、わかりやすく解説いたします。
【朝廷は、天皇による政治機関】のことです
朝廷と同じく、よく耳にする【幕府】となにが違うのでしょうか?
幕府とは、武士による【臨時の政府】のことなのです
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
朝廷とは何か?分かりやすく解説いたします
朝廷とは、天皇を中心に政務を行う組織または場所のことです。
よく大河ドラマなどに登場する朝廷という言葉をご存知でしょうか。
朝廷とは、いったい何のことなのでしょうか?
まずは朝廷という言葉を、二つに分断してみます。
【朝】とは、政治のこと。
そして【廷】とは、お庭のことです。
政治は朝に行うもの、といわれていました
昔の皇帝や天皇は、大変早起きでした。
朝日が昇ると同時に、政治を行う権力者は、部下を庭に集めて政務を開始したのです。
そしてもう一つ、朝廷という言葉が意味するところとして、天皇がおられます。
朝廷とは、すなわち
天皇を中心として、政務を行う機関・場所のこと
と言いかえることができます。
幕府との違いとは?
幕府とは、朝廷から政治をおこなう権限を与えられ、代わりに政治をおこなう臨時の機関のことです。
朝廷と対比する言葉として、幕府というものが歴史に登場します。
朝廷と幕府は、何が異なるのでしょうか?
と、日本の歴史には、3つの幕府が存在しています。
幕府とは
朝廷から、政治を行う権限を委譲された征夷大将軍が、朝廷に代わって政務を執り行う臨時の機関
のことです。
もともと政務を行う権限は、朝廷が持っていました。
幕府は、政務をおこなう権限を朝廷からあたえられた臨時の機関なのです。
征夷大将軍は、そもそも異民族の敵を征伐するための臨時の職務です。
そのため、征夷大将軍が開くものである幕府もまた、臨時の機関なのです。
大政奉還をご存知でしょうか?
江戸幕府最後の将軍・徳川慶喜が、政治をおこなう権利を朝廷に返上した大事件です。
返上するという言葉からわかる通り、もともと政治を行う権限は幕府ではなく、朝廷が持っていたものなのです。
- 朝廷は公家
- 幕府は武家
元々はお公家さんのほうが身分は上でした。
しかし武家は、平清盛や織田信長などに代表されるように、武力と財力でもって、公家も逆らえないほどの力を持つようになります。
武家は、力で公家を押さえつけて、政治を行う権限を幕府という形で一時的に手にしていたのです。
朝廷は、今の日本にもあるの?
結論から申しあげますと、現在の日本に朝廷はありません。
現在の議院内閣制の日本国においても、朝廷というものは存在しているのかを、一度考えてみましょう。
現在の日本には、もう朝廷は存在しません。
大政奉還はすでにご存知かと思いますが、【王政復古のクーデター】をご存知でしょうか?
大政奉還も王政復古も、幕末の日本で起こった歴史的事件です。
このときに、幕府という政治システムが廃止されました。
同時に、古来の日本で行われていた政治システムである太政官制が復活しました。
しかし【1885年(明治18年)12月】、太政官制は廃止されます。
そして新しい政治システム内閣制度が始まりました。
この年、伊藤博文が日本最初の内閣総理大臣に就任し、政治を行う機関としての朝廷は完全に消滅しています。
それ以降、日本では議院内閣制が採用されており、天皇陛下と皇室は存在するものの、朝廷は存在しておりません。
幕府とは何か?もっとくわしく、わかりやすく解説!
幕府とは、武士が自分にとって都合の良い政治をおこなうためにつくった臨時の政府です。
幕府が何なのか、もっとくわしく、わかりやすく解説いたします。
まずは軽くおさらいしてみましょう。
先ほども申しましたが幕府とは、臨時の政府のことです。
政府とは、政治をおこなう組織のことです。
幕府とは、本来はあるべきではないが、臨時につくられた政府のことです。
臨時ということは、本来の政府もあるはずです。
その本来の政府が、朝廷です。
では、どうして幕府という臨時の政府が誕生したのでしょうか?
どうして幕府が必要だったのか?
幕府が誕生した理由は簡単です。
幕府は武士たちがつくったものなのですが、その武士たちが自分たちにとって都合の良い政治を行うために臨時の政府である幕府をつくったのです。
もともと日本では朝廷が政治を独占していました。
政治とは法律をつくったり、軍を動かして戦争をしたり、国の行く末を決めることです。
その政治をかつての日本では、朝廷と、朝廷のメンバーであるお公家さんが独占して行っていたのです。
お公家さんが政治を行うと、どういうことが起こると思いますか?
お公家さんたちが政治をおこなうと、お公家さんにとって都合の良い政治が行われるようになるのです。
これは武士が政治をおこなっても、同じことが起こります。
武士にとって都合の良い政治が行われるようになるのです。
たとえば藤原道長は、摂関政治という政治のやり方で、自分にとって都合の良い政治を行いました。
そして権力を独占することに成功します。
「この世は私のための世だ」
と歌うほどに、栄華を極めました。
次に院政と呼ばれる政治を行った白河法皇も、自分にとって都合の良い政治を行いました。
- 鴨川
- サイコロ
- 山法師
この3つ以外、すべて私の思いのままだ
と言うほどに、力を持っていました。
また、平清盛たち平家一門も、政治を独占すると、自分たちにとって都合の良い政治を行うようになります。
「平家一門ではないものは、人ではない」
と言うほどの権勢を誇ったのです。
このように政治を行うものは、自分にとって都合の良い政治を行うようになる習性があります。
令和の現代でも、それは変わりません。
政府機関のなかで最大の力を持つ自民党は、自分たちにとって都合の良いように政治を、内閣という政府に行わせています。
お公家さんや法皇が政治を独占して権勢を誇っているあいだ、武士たちは彼らのボディーガードとして、こき使われる有様でした。
武士はいくら頑張っても、奴隷のようにこき使われるばかりで、自分たちにとって不利な政治やられてばかりだったのです。
それに不満をいだいた武士たちは、自分たちにとって都合の良い政治をやりたいと思うようになります。
平清盛は、朝廷の重要な役職を、自分の血縁者である平家一門で独占するというやり方で、自分たちにとって都合の良い政治をやろうとしました。
しかしこの方法では、朝廷の絶対権力者である天皇や上皇に邪魔されて、自分の好きなように政治ができないのです。
実際に平清盛は、後白河法皇に邪魔され、うまく政治ができていません。
清盛のライバル・源頼朝は、平清盛とは違った形で、自分たちにとって都合の良い政治をやろうとします。
その方法が、幕府を開くという方法だったのです。
幕府という臨時の政府をつくりあげて朝廷から、政治をおこなってもいいよ、という許可を得れば、天皇や上皇に邪魔されず、好きなだけ自分たちにとって都合の良い政治がおこなえます。
その許可こそが、征夷大将軍に任命されるということだったのです。
征夷大将軍は、遠いところにいる敵を倒すために、臨時に任命される将軍のこと。
遠いところにいる敵を倒すためには、いちいち天皇にあれこれと許可を求めていては、時間がかかって敵に勝てません。
そのため征夷大将軍には、自分の好きなように政治をおこなって良い、という特権が与えられていたのです。
源頼朝は、この征夷大将軍の特権に目をつけて、征夷大将軍の位を求めたのでした。(正確に言えば、頼朝は特権を持つ大将軍なら、なんでも良かったらしい)
征夷大将軍の位を与えることが幕府をつくることにつながるとわかっていた後白河法皇は、征夷大将軍の位を頼朝に与えたくありません。
そのため、後白河法皇が亡くなった1192年まで、頼朝は征夷大将軍になれませんでした。
逆に言えば、後白河法皇が亡くなったから、1192年に、源頼朝は征夷大将軍になることができたのです。
源頼朝が征夷大将軍となって鎌倉幕府を誕生させた【1192年】から、明治維新で江戸幕府が滅びる【1868年】までの676年間、日本は幕府という武士たちによる臨時の政府によって支配され、政治が行なわれていきました。
近年では、鎌倉幕府の誕生は1192年ではなく、1185年といわれています。
朝廷つまりお公家さんたちは、これが面白くありません。
そのため、幕府から政治を行う特権を取り戻そうとする動きがしばしば起こります。
- 1221年、後鳥羽上皇による承久の乱
- 1333年、後醍醐天皇による建武の新政
などがそれです。
お公家さんとつながった薩摩藩・長州藩による明治維新もそうです。
明治維新によって
という武家による政権は、終わることとなるのです。
幕府とは、武士たちが、自分たちにとって都合の良い政治を行うための臨時の政府です。
政治とは、それを行う者にとって都合よく行われる
と申しましたが、今もそれは変わりません。
しかしその形は、昔に比べて非常に巧妙に、しかもわかりにくく隠蔽されています。
今現在、自分たちにとって都合のよい政治をおこなっているのは、国民から選挙で選ばれた政治家です。
特に小選挙区制という、地元に強固な地盤を固めた世襲議員にとって都合の良いシステムが定められた現在、日本の政治は代々の政治家一族にとって、とても都合良く行われていると言って良いでしょう。
人間の本質は、長い歴史の中で、何も変わってはいないのです。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 朝廷とは、天皇を中心として政治を行う執政機関のこと
- 幕府とは、朝廷から政治を行う権限を委譲された、征夷大将軍を中心とする臨時の執政機関のこと
- 21世紀の日本において、朝廷は存在しない
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
よろしければ以下のリンク記事も、お役立てくださいませ。
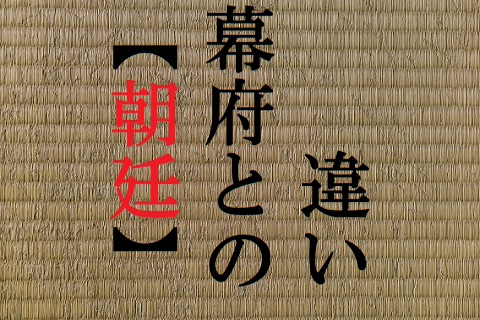
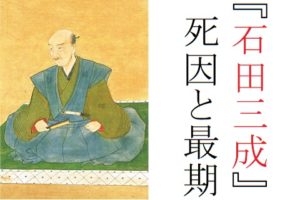

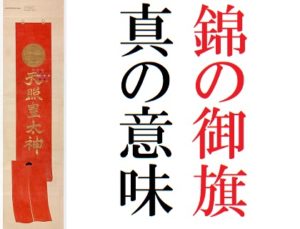





コメント
コメント一覧 (3件)
レキシルの記事を読み、学習し、自分の意見などを投稿してきた。翌日には返事があり、充実した毎日であった。しかし、GW後は、以前のように返事を書けないということであった。現在、投稿しても返事がないので、虚無感というか脱力感に陥っている。めげずに、自分を鼓舞して足跡を残すために投稿は続けようと思う。
⑴勉強になったこと
①書き出しの3行目が、「体言止め」になっている。調べてみると、簡潔な表現ができる、余韻を残すことができる、イメージの広がりを演出することができると書いてありました。勿論、デメリットもあるそうです。多用はいけませんとか、体言止めで終わった場合に。を付けるのはいけない、論文には不向きであるとか書いてありました。知りませんでした。
②《朝廷とは何か?》の5行目に「大変」早起きとある。私ならば、「とても」早起きと書きます。「とても」と言えば、「ドラえもん」の歌には、「とっても大好き」とある。「とても」と「とっても」の違いを知りました。「とっても」は、好きであることを強調する表現ではあるが、文章を書く時には不適切らしい。
③《幕府とは何か?、、、》の26行目に次に「院政と呼ばれる政治を行った「白河法皇」とある。私ならば「白河上皇」と書く。調べてみると、「白河天皇」は「白河上皇」になり、出家して「白河法皇」となっているので誤りではない。高校時代に「法皇」であり「法王」とは書かないと教わったが、「白河法皇」は、「禅定法王」ともいうことは、知らなかった。
⑵疑問に思ったこと
①疑問のスタートは、《幕府とは何か?、、、》の34行目に「令和」の現代とある。私ならば、「令和」の現在と書く。それ以上に「えっ!」と思ったのは、この記事は、2018年6月27日に書かれた記事である。「令和」という元号が決定されたのは、2019年4月1日である。2018年の時点で「令和」という元号を書いてあるのはなぜだろう。
②この記事を短く言うとの1行目「朝廷」とは、点がある。2行目「幕府」とは点がない。
③《幕府とは何か?、、、》の4行目に「政府」とはには点がない。5行目には「幕府」とはには点がある。
⑶個人的な意見
白河法皇(上皇・院)の歌「鴨川の水、山法師、サイコロ」とある。高校時代に「山法師」とは何かという問題が出たことを懐かしく思い出した。また、「やまほうし」で「やまぼうし」ではないと習った。(どちらでも良いようだ)
更に調べてみると、私の頃とは違っている。これは、「天下三大不如意」と習ったが、正式には、「天下三不如意」が正しいようだ。却下されると思うが、「サイコロ」は、「双六の賽」と書くべきだと思う。「鴨川の水」以下の順番も気になる。また、この歌には説明が必要だと思う。理由は、「山法師」の意味を検索すると、「山法師(やまぼうし)」という花が最初出てきて分かりにくい。「鴨川」に関しても、専門家は、「賀茂河」と書いている。
[…] 「【朝廷とは】世界一わかりやすく簡単に解説!幕府との違いはなに?」の記事はコチラ スポンサーリンク (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || [ […]
[…] 幕府は、朝廷という本来の政府から、政治を行う権限を任されている、武士たちの武士たちによる武士たちのための政府。 […]