『m』
『織田信長』が天下取りの道を駆け上がるきっかけとなった「桶狭間の戦い」。
その桶狭間の戦いで、今川義元の首を取ったといわれる武将は誰なのでしょうか?
敗れた『今川義元』の首は、信長の居城・清州城下でさらされましたが、その後はどうなったのでしょう?
駿府城に持ち帰られたとされている今川義元の首ですが、実は愛知県内に首塚があるのです。
この記事では、なぜ今川義元は織田信長に敗れ、そしてなぜ首塚が愛知県にあるのか、あまりご存じない方のために、わかりやすく解説していきます。
これを読んで「そうだったのか、今川義元と桶狭間の戦い!」と、疑問をスッキリと解消してくださいね。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
拙者は当サイトを運営している「元・落武者」と申す者・・・。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
桶狭間の戦いで、今川義元の首を取ったといわれる武将は?
今川義元の首を取ったといわれる武将は、毛利新介良勝です。
毛利新介は、織田信長の馬廻役または小姓だったといわれています。
桶狭間の戦いで、今川義元を最初に負傷させたのは、服部小平太一忠という武将でした。
しかし服部小平太が膝を斬られて負傷。
これを助けた毛利新介が、今川義元の首を取って名乗りをあげたといいます。
毛利新介はこのとき、今川義元に指を食いちぎられたといいます。
その後、毛利新介は織田信長につかえつづけ、桶狭間の戦いから22年後の1582年、本能寺の変で織田信長・信忠親子と共に戦死します。
服部小平太はというと、信長の死後は秀吉につかえて大名になったものの、豊臣秀次の謀反疑惑に加担したといわれて1595年に切腹しています。
今川義元の首はどこへ?義元の家来「岡部元信」が駿府へ持ち帰った
【1560年6月12日】、桶狭間(愛知県名古屋市緑区)で、大軍団を率いていた『今川義元』は、わずかな手勢を率いた『織田信長』に討ち取られました。
大将を討ち取られた今川軍は総崩れとなり撤退。
これが、史上最大の大番狂わせと言われる合戦『桶狭間の戦い』です。
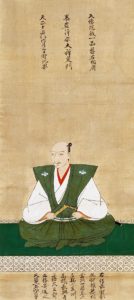
織田信長
引用元ウィキペディアより
この日をさかのぼること約1ヶ月前、今川義元は尾張の織田信長を攻めるため、自ら大軍を率い、駿府城(静岡県静岡市)を出発しました。
【6月11日】、『松平元康(のちの徳川家康)』に命じ、大高城(名古屋市緑区)に兵糧を届けさせます。

徳川家康
引用元ウィキペディアより
さらに義元は、【翌6月12日】午前3時頃に、松平元康に織田軍の砦を攻撃させました。
前日、今川軍接近の報せを受けても清州城で籠城するか、または討って出るかを決めかねていた信長は、この報告を聞いて飛び起きます。
史料には残っていませんが、織田家に人質として預けられていた際に信長が弟のように可愛がっていた『松平元康』が、織田軍に弓を引いたと聞いて、あわてたのかもしれません。
午前4時頃に清州城を出立した信長は、午前8時に熱田神宮に到着。織田軍を集結させ、戦勝祈願を行います。
午前10時頃、鳴海城(名古屋市緑区)を囲む砦に到着した信長は3千程度の軍勢を整えました。
松平元康軍に攻められた砦では、織田家の有力な家臣が戦死し、今川軍は大高城周辺の制圧に成功。
義元は本軍を率いて大高城方面を目指して進み、そのあと南下。「桶狭間」方面に進みました。
この報せを受けた信長も、東南に進軍して「桶狭間」を目指します。
午後1時頃、視界を奪うほどの豪雨が桶狭間一帯に降り注ぎました。
『信長公記』に「石水まじり」と記録されていることから、「ひょう」が混じった豪雨だったのでしょう。
信長は「梅雨将軍」という異名をつけられるほど、大切な戦いのときには、常に雨を味方にする武将でした。
あの「長篠の戦い」でも、開戦直前まで大雨が降っていたと言われています。
話を戻しましょう。
この豪雨の中で信長は、今川義元の本隊と激突。
今川軍の総数は1万5千とも2万とも言われていますが、義元本人を守る本隊の手勢は、5千人程度でした。
一方の信長軍は3千人程度でしたが、数では拮抗していたと言えるでしょう。
次々と兵を討ち取られた義元は親衛隊に守られながら騎馬で逃れようとしますが、信長の馬廻衆(親衛隊・精鋭部隊)に追いつかれました。
それでも今川義元は奮戦。槍で攻撃してきた信長の馬廻衆の一人『服部一忠』の膝を切り、返り討ちにしましたが、『毛利良勝』に組み伏せられ、首を打たれたのです。
首を打たれる際、義元は「毛利良勝」の左手の指を食いちぎったと言われています。
大将を討ち取られた今川軍は動揺し、総崩れとなりました。
次々と本拠地の駿河・駿府に逃げ帰り、大高城を守っていた松平元康は城を抜け出て、三河国・岡崎にある松平家の菩提寺「大樹寺」で自害しようとしましたが、住職の「登誉上人(とうよしょうにん)」にいさめられ、岡崎城に逃げ込んだのです。
討ち取られた義元の首はきれいに洗われ、信長のもとに届けられました。
当時、武将は負ければ首を討たれることを覚悟して生きていたのです。
首を討ち取った側でも、首をきれいに洗い、死化粧をほどこして敵に対する敬意を表していました。
首実検の終わった義元の首は清州城下にさらされましたが、鳴海城に籠城し、義元亡き後も戦い続けていた今川家重臣『岡部元信』が鳴海城を引き渡す代わりに義元の首の返還を求め、信長がこれに応じたのです。
こうして、鳴海城を明け渡した岡部元信は、主君の首を取り戻し、駿府への帰途につきました。
互いに戦いで敗れれば首を討たれる覚悟はしていても、やはり主君の首をさらされるのは、臣下としては辛いものがあったのでしょう。
たとえば、『大坂夏の陣』で自刃した『豊臣秀頼』の介錯は『毛利勝永』がつとめました。
追手門学院の校舎拡張工事で発掘された『顎に刀傷のある丁寧に埋葬された頭蓋骨』はその特徴から、豊臣秀頼のものだと言われています。
おそらく、介錯した毛利家が徳川軍に奪われないように隠れて埋葬したのでしょう。
それほどに、主君の首を奪われるのは武将にとって忍びないことだったのです。
一方、首を討ち取られ桶狭間の戦場に放置された義元の遺体は、今川家の家臣が回収し、丁重に葬るために駿府に持ち帰ろうとしました。
しかし遺体の腐敗が激しく、家臣たちは駿府まで持ち帰ることを諦め、駿府までの途中、愛知県豊川市の牛頭山『大聖寺』に葬ったのです。
それが、この節の冒頭の写真「今川義元の胴塚」です。
この記事で旧暦ではなく、グレゴリオ暦(現在私達が使っている太陽暦)で日付を書いています。その理由は、当時の「季節」を考えて読んでほしいためです。
義元の亡くなった6月12日は、梅雨時ですよね。
梅雨時の蒸し暑くジメジメとした気候は、この記事を読んでいる方もよくご存知でしょう。
湿度も高い時期、野外で雨に何度も濡れた遺体の腐敗の進行は早かったはずです。遺体を持ち帰るのを諦めたのは致し方のないことでした。
では、『岡部元信』が信長から返還された義元の首はどうなったのでしょう?
次節で見ていきましょう。
駿府へ帰ったはずの義元の首!なぜか愛知県に首塚があった
織田信長は岡部元信の主君を思う心根にうたれ、義元の首を棺におさめて返還しました。
受け取った元信は、駿府を目指して帰還を始めたのですが・・・。
戦功のないまま駿府に戻ることを恥と考えた元信は、刈谷城(愛知県刈谷市)の水野信近(徳川家康の母方の叔父)を攻め、討ち滅ぼします。
この元信の戦功に対し、義元の子『今川氏真』が旧暦6月8日付けで、所領の加増を伝える感謝状が残っているのですが、旧暦の6月といえば、グレゴリオ暦では7月にあたります。
元信が信長から返還された首を携えてまっすぐ駿府に帰らず、刈谷城を攻めたことで義元の首の腐敗は進行してしまったはずです。
【6月12日】に亡くなってから半月も経っているのですから。
蒸し暑い梅雨時のことですから、駿府に持って帰るのを諦めなければならない状況になってしまったのでしょう。
駿府に持って帰るのを諦めた義元の胴体と同じように、首も駿府までの途中で埋葬することになったのでした。
今川義元の叔父『徳順上人』が住職をしていた東向寺(愛知県西尾市)に立ち寄った岡部元信は、首を東向寺に埋葬。主君の首を守るため、2名の武将が墓守として寺に残ったのです。
その2名の武将のうち、今村という武将の子孫はその後も墓を守り続け、昭和の初めまで東向寺の檀家として存続していました。
とはいえ、今川家の菩提寺・臨済寺(静岡県静岡市)でも、主君を弔い墓所を築かなければなりません
そのため、胴体の方は着ていた鎧や具足、首の方は髪の毛などを遺体から取り、駿府に持ち帰ったのでしょう。
こうして、今川義元は『首塚』『胴塚』『菩提寺の墓所』と、あちこちに墓所が残ることになったのです。
念の為、以下に「今川義元」にゆかりのある塚やお寺の位置を示す地図を掲載しておきます。
これら以外にも『愛知県東海市』には、桶狭間の戦いで討たれた今川義元の胴体を埋めたと伝えられる『今川塚』が残っています。

【伝:今川義元首塚(愛知県西尾市東向寺):WikipediaよりBaristonによる撮影】
4万の義元軍は、なぜ桶狭間で敗北したのか?敗因は『偶然』
これまで、桶狭間の戦いで織田信長が勝利した理由として、「迂回攻撃説」と「正面攻撃説」の2つが唱えられてきました。
「迂回攻撃説」は、義元が桶狭間の「田楽狭間(でんがくはざま)」と呼ばれる窪地で休息を取っていることを信長が知り、気付かれないように背後に周り、奇襲攻撃を仕掛けたというものです。
緒戦の勝利で気を良くしていた今川義元が油断していたとも言われていますが、それを示す同時代の史料はありません。
今川義元は『戦上手の武将』として知られ、戦場で油断するということは考えにくいのです。
ただ、手勢の少ない織田軍が油断した今川軍を攻め滅ぼす姿は、創作物(例えば小説など)では非常に劇的で感動を呼ぶでしょう。
こうして、今川義元が油断しているところを織田信長が僅かな手勢で攻め滅ぼした「迂回攻撃説」は、長年受け入れられてきました。
一方、「正面攻撃説」は、信長の部下『太田牛一』の『信長公記』に書かれた記述をもとにして考えられたもので、桶狭間で見つけた敵軍を沓掛城(くつかけじょう)から出てきたばかりの義元本隊とは知らず、形勢逆転を狙って攻撃を仕掛けたと唱えられたものです。
「正面攻撃説」では、織田信長の情報収集能力が長けていたと主張する学者もいますが、今川義元の戦場での居場所が一定していたとは言えないことから、否定的な見解もあります。
しかし、近年は「正面攻撃説」が主流を占めています。
今川軍からすると城を出たばかりの豪雨の戦場で、ばったりと敵の大将がひきいる本軍に出会い、手勢も拮抗していたために苦戦を強いられ、大将を討ち取られてしまったということです。
一方の織田軍からすると、織田家の有力家臣を討ち取られ、形成不利な状況の中、豪雨の戦場でばったり出会った敵軍を、形勢逆転のために攻撃を仕掛けたら、それがたまたま敵の大将だった。
つまり、今川義元には不運が重なり、逆に織田信長には幸運が重なり、その結果として史上最大の大番狂わせ「桶狭間の戦い」が生まれたと考えられているのです。
ですが、筆者は少し違う意見を持っています。
信長にとって幸運が重なったのは確かにあったかもしれませんが、当時の名古屋市緑区『鳴海』『大高』『桶狭間』のあたりは、今よりもずっと海岸線が近かったのです。
信長は鷹狩を好み、桶狭間や鳴海、大高のあたりでもよく鷹狩を行っていました。
つまり、今川義元よりも、あたり一帯の地形や気象に詳しかったのです。
今よりも海が近かったということは、時間帯によっては海風が強くなることもあるでしょう。
それらを熟知していた信長は、海風の強くなる時間帯に大声を出し、実際よりも兵の数を相手方に多く思わせて動揺を誘い、降り出した豪雨を味方につけて攻めたのだと思います。
「明智光秀」の末裔で歴史研究家の「明智憲三郎」さんも、信長が攻撃を仕掛けた相手がたまたま「今川義元」の本軍だったのではなく、「孫子」「呉子」などの兵法を熟知していた信長が、それらの兵法書に記されている
「狭い道に布陣した敵に、追い風や雨のなかで、大声を上げて攻撃せよ」
という方法を守って、正攻法で攻撃したところ、義元を打倒した・・・・と著書「本能寺の変・431年目の真実」で主張しておられます。
もしかしたら、そうやって攻めた相手が、たまたま運良く義元本隊だったのかもしれませんが『運も実力のうち』です。
『桶狭間の戦い』は、一帯の地形や気象を熟知していた信長が、手勢は少なくとも戦う条件としては義元より有利だったとも言えます。
『今川義元』について「ひとこと」言いたい!
実は筆者は子供の頃、愛知県名古屋市緑区に一時期住んでいたことがあります。
名古屋市の中では自然が多く残る緑区は、史跡が多く残る場所でもありました。
「鳴海城」「大高城」「桶狭間の古戦場」さらに緑区の隣の南区には「笠寺城」があり、戦国時代の武将である「今川義元」「織田信長」「徳川家康」にゆかりの史跡が数多くあったのです。
戦国時代の史跡が数多く残っていること、また父親が戦国時代を描いたドラマが好きだったこともあり、戦国時代に興味を持ち、書籍を読み漁ったことがあります。
「なんで今川義元のお墓があちこちに残っているのだろう?」と疑問を持って調べたことがあり、今回の記事を書きながらそういえば、子供の頃に調べたなぁと懐かしく思い出しました。
亡くなった時期が蒸し暑い梅雨時で、遺体の腐敗は秋や冬よりもずっと早く進んだことでしょう。
気温と湿度が、義元の遺体が駿府に戻ることを阻んでしまったのです。
豊川市に残る首塚と胴塚はいずれも信憑性が高いものだと思います。
特に、首塚の方は墓守として残った家臣の子孫の家系が、昭和の初めまで伝わっていたことが東向寺の過去帳で確認されていますから。
「桶狭間の戦い」で「織田信長」に敗北したことで過小評価されている「今川義元」ですが、近年、桶狭間の戦いの研究が進んだことで、義元の評価も変化し始めました。

今川義元
引用元ウィキペディアより
ドラマなどで、お歯黒のお公家さん風のキャラクターに描かれることが多い今川義元ですが、実際は「武田信玄」や「北条氏康」と義兄弟。戦も上手で「海道一の弓取り」と謳われる名将だったのです。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 今川義元の首は、義元の部下「岡部元信」が、交渉によって、「鳴海城の明け渡し」を条件に織田信長から奪還していた。
- 今川義元の首はその後、梅雨時の気候で首の腐敗がすすんだため、本拠地の駿府まで帰れず、やむなく「愛知県西尾市」の「東向寺」に埋葬された。
- 義元の敗因は、信長による「偶然の奇襲」と言われているが、信長の計算され尽くした奇襲によるものではないか
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
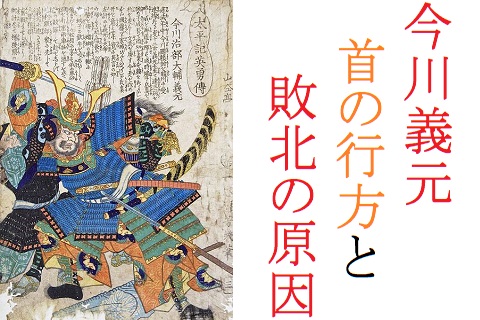






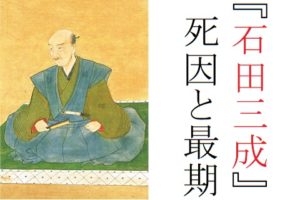

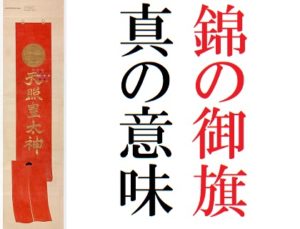





コメント