なぜ「太平記」はタブーとされてきたのでしょうか?
その背景には、日本の皇室の正統性をめぐる複雑な歴史があります。
この記事では、その理由を最新の研究成果とともに分かりやすく解説していきます。
太平記がタブー視された背景
問題の根源は、南北朝時代という特殊な時代にありました。
14世紀の日本では、南朝と北朝という二つの朝廷が並び立っていたのです。朝廷が二つあるということは、つまり天皇が二人いたということです。
長い間、「南朝こそが正統で、北朝は偽物」という考え方が主流でした。
しかし現在の天皇陛下は北朝の系統にあたるため、ここに大きな矛盾が生まれました。
南朝を正統とすれば、現在の皇室の正統性に疑問符がついてしまう。
この矛盾こそが、太平記をタブー視する最大の理由だったのです。
この南朝正統論が生まれた背景には、楠木正成という武将の存在があります。

引用元ウィキペディアより
南朝の後醍醐天皇に最後まで忠義を尽くした正成の生き方が、理想的な武士像として崇められてきました。
そのため、正成が仕えた南朝こそが正しいという論理が形成されていったのです。
明治政府が作り上げた「正統論」
この問題をさらに複雑にしたのが、明治時代の政治的な事情でした。
大日本帝国憲法には「万世一系の天皇」という言葉があります。
つまり、日本には古代から途切れることなく続く一つの皇統があるという建前です。
ところが南北朝時代には明らかに二つの皇統が存在していたため、どちらが正統かを決める必要に迫られました。
明治政府は江戸時代の水戸学の影響を受け、南朝正統論を採用します。
特に維新の原動力となった長州藩は楠木正成を理想化しており、天皇中心の国家観形成に大きな役割を果たしました。
しかし、ここで新たな矛盾が生まれます。
南朝が正統なら、北朝系の明治天皇の正統性はどうなるのか?この政治的な矛盾を隠すために、南北朝問題は慎重に扱われるようになったのです。
「太平記」という作品の特殊性
太平記は室町時代に成立した歴史文学で、後醍醐天皇の即位から足利義満の時代までを描いています。

引用元ウィキペディアより
この作品の問題点は、南北朝の対立を生々しく描いていることでした。
1991年にNHK大河ドラマ「太平記」が放送されましたが、これは画期的な出来事でした。
なぜなら昭和時代まで、「天皇と戦う主人公」や「天皇が悪役として描かれる物語」は絶対的なタブーだったからです。
戦前・戦中の教育では南朝正統論が国是とされていたため、この時代を扱う歴史ドラマや小説は極めて慎重な配慮が求められていました。
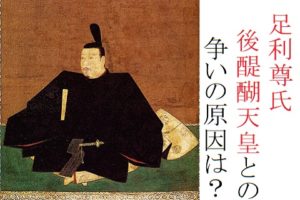
現代の新しい視点(2025年現在)
時代は大きく変わりました。
現在の歴史研究では、「南朝だけが正統」という単純な見方は見直されています。
最新の研究成果によると、北朝側にも十分な正統性と歴史的根拠があることが明らかになってきました。
また太平記についても、史実と創作が巧妙に混ぜ合わされた文学作品であることが改めて確認されています。
2025年現在、多くの専門家や教科書では
「南北両朝の歴史的意義を対等に評価し、どちらか一方だけを正統とする判断は適切ではない」
という見解が主流となっています。
英雄像の変遷:楠木正成と足利尊氏
歴史上の人物評価も時代とともに大きく変化しています。
楠木正成は長らく「忠臣の鑑」として理想化されてきました。
特に明治維新期や戦前には、天皇への絶対的な忠義を示す象徴的存在として扱われました。
現代では、優れた戦略家や地域リーダーとしての側面にも注目が集まっています。
一方、足利尊氏は「逆賊」というレッテルを貼られることもありました。

引用元ウィキペディアより
しかし近年の研究やドラマ化により、「新しい時代を切り開いた創造者」として再評価が進んでいます。
両者とも、時代の政治的な必要性によって評価が左右されてきたため、単純な善悪で判断することは適切ではありません。
多様な歴史観の重要性
武士道や忠義の概念も、時代とともに変化し続けています。
現代の歴史教育では、「多角的な視点」と「複眼的な人物評価」が重視されています。
もはや「忠義一辺倒」や「皇国史観」だけでは理解できない、複雑で多面的な歴史像が求められているのです。
太平記や南北朝時代は、日本における「正統性とは何か」「英雄とは何か」「歴史の多様性」を考える貴重な教材となっています。

まとめ
太平記と南北朝時代をめぐるタブーは、時代の変化と研究の進展により大きく様変わりしました。
現代では、物語と史実をきちんと区別した上で、様々な視点から歴史を捉えることの重要性が認識されています。
かつてのタブーは、今や日本の歴史観や価値観の多様性を学ぶ貴重な機会となっているのです。


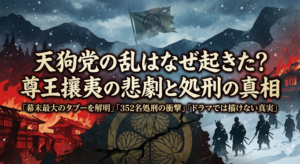
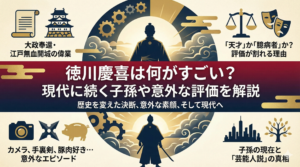
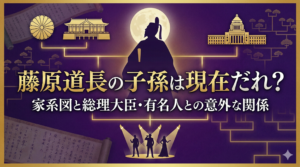

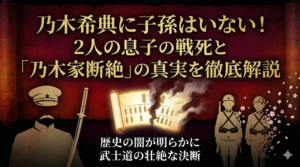

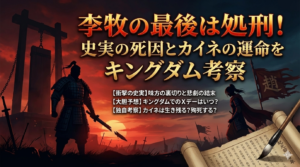
コメント