今回のテーマは徳川家康です。
この記事では徳川家康の凄さについて、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。
これを読めば、なぜ家康が天下取りに成功したのかを、カンタンに理解できます。
徳川家康は他人の幸福を最も大切にしたからこそ、天下取りに成功したのです。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
1,徳川家康のすごいところ①
徳川家康はとても我慢強い人だった。そのため、数々の苦難を乗り越えて、最期には天下を取ることに成功した。
2,家康のすごいところ②
家康は、織田信長や武田信玄の失敗や、自分自身の失敗からも学び、同じ失敗を繰り返さないように、改善を繰り返していた
3,家康のすごいところ③
家康は【厭離穢土・欣求浄土】というスローガンの通り、他人の幸福を最も大切なものとしていた。最後には天下取りに成功し、平和な時代を作り上げることに成功した。
徳川家康のすごいところを、簡単にわかりやすく解説
織田信長・豊臣秀吉に続き、最後に天下を取った徳川家康
そのすごいところは数限りなくたくさんあるのですが、特にすごいところを3つだけピックアップしてみたいと思います。

《徳川家康》
「引用元ウィキペディアより」
家康のすごいところ3つをザッと申し上げると、以下の通りです。
- 忍耐力
- 自分と他人の失敗から学び、改善する
- 他人の幸せを最優先とする
徳川家康には、織田信長や豊臣秀吉に比べると、ヒーローと呼ぶにはふさわしくない失敗がたくさんあります。

《織田信長》
クリックすると拡大できます
「引用元ウィキペディアより」
そのため、信長・秀吉よりも人気が劣ります。
しかし最期には、世界史上でも珍しいほど長期の平和な時代をつくりあげ、天下万民を幸福へと導いたのです。
信長・秀吉・家康たち三英傑と呼ばれる三人の中でも、最も人類に貢献した人物なのではないでしょうか。
(ただし、家康が亡くなったあとの江戸時代は結果として、自由と豊かさを失った日本史上でも屈指の最悪な時代だったと筆者は思っている)
→→→→→【織田信長は何をした人なのか】についてくわしくはこちら
徳川家康の凄さ・その①忍耐力
徳川家康のすごいところといえば、忍耐力でしょう。
鳴かぬなら鳴くまで待とう時鳥
そう歌われたように、家康はとても我慢強い人なのです。
織田信長との同盟によって家康は、強敵・武田信玄からの盾として利用されてしまいました。

《武田信玄》
「引用元ウィキペディアより」
クリックすると拡大できます
それにもかかわらず家康は、信長との同盟締結から武田家滅亡までの、実に20年もの間、最強・武田軍団を防ぎ続けたのです。
その忍耐力は、並のものではありません。
それだけではありません。
【1582年】、本能寺の変で織田信長が亡くなると、家康は天下人・豊臣秀吉の圧力におされて、臣従を余儀なくされます。
家康は、それまで苦労に苦労を重ね、血と汗と涙で手に入れた東海5カ国、すなわち
- 三河
- 遠江
- 駿河
- 甲斐
- 信濃
この5カ国を、秀吉に取り上げられてしまうのです。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)
「引用元ウィキペディアより」
代わりに与えられたのが、後北条氏の善政によって治められていた関東の未開の地でした。
(北条氏の善政になついていた関東は、北條氏を滅ぼした家康にとって、とても治めにくい土地だった)
家康は、この未開の地を開拓し、ついには世界一の大都市・江戸の基礎をつくることに成功します。
武田家の圧力・秀吉の圧力その他、数々の逆境にさらされた家康。
それでも自暴自棄になることなく、決して諦めることなく、最期には天下取りという最大の成功を手に入れているのです。
→→→→→【本能寺の変と家康の伊賀越え】についてくわしくはこちら
徳川家康の凄さ・その②自分と他人の失敗から学ぶ
家康は、自分と他人の失敗から学び、それを活かすことに、とても優れていました。

三方ヶ原の戦いで敗北し逃げ帰った徳川家康肖像:徳川美術館所蔵、wikipediaより、パブリックドメイン
たとえば本能寺の変で、織田信長は嫡子・織田信忠と一緒にいたため、そろって明智光秀に討ち果たされてしまいました。
もしも織田信忠が生きていたら、織田家が豊臣秀吉に乗っ取られて没落するようなことには、ならなかったはずです。
(ただし、歴史家・本郷和人先生は、信忠が生きていても、秀吉に天下を奪われていただろうとおっしゃっておられます)
【1598年】、豊臣秀吉が死去すると、家康は一緒に近畿地方にいた後継者である徳川秀忠を、遠く江戸まで大急ぎで移動させています。
秀吉の死によって、混乱が起こるかもしれないと思った家康は、秀忠を安全な本拠地・江戸へ避難させたのです。
もし万が一、家康が何かしらの理由で命を落としても、後継者である秀忠が生きていれば、徳川家は安泰だからです。
(実際に家康は、前田利家や石田三成によって、何度も命を狙われたという説がある。)
武田信玄の失敗からも、家康は貪欲に学んでいます。
信玄といえば、家康がもっとも長く苦しめられた宿敵です。
その武田信玄は【1573年】、天下取り目前で病死してしまうのです。
家康は、このとき三方ヶ原の戦いで大敗しているのですが、病死した信玄の二の舞にならないようにと気をつけたのか、健康にとても気を使っているのです。
- 趣味の鷹狩によって身体を動かし
- 薬の調合を趣味として健康に気を配り
- 感染症を予防するために遊女を遠ざけて出産経験のある女性を側室に選び
- 食事は常に栄養を考えて贅沢な食事はせずに粗食とし、常にあたたかいお味噌汁を欠かさずに体温を上昇させる
などなど、健康にこだわりみせています。
他にもあります。
家康は三方ヶ原の戦いで大敗した自分の姿を、絵師に描かせて、しかみ像と呼ばれる絵を、後世にまで残しています。
この大敗で、家康は大便を漏らしながら逃げ帰ったといわれています。
大失敗を絶対に忘れないように、この絵を身近において忘れず、後の大成功に活かしたのでした。
(一説によると、このしかみ像の絵は、家康の死後、後世に描かれたものである可能性があると、歴史家・小和田哲男先生がおっしゃっておられました)
徳川家康の凄さ・その③他人の幸せを最優先とする
徳川家康は、自分よりも民衆・天下万民の幸せを優先した人でした。
これは徳川家康という人の、一番いいところだと思います。
最も多くの人間を喜ばせたものが、最も大きく栄える
これは家康が残した言葉といわれています。
徳川家康といえば、江戸時代【263年】にも及ぶ天下泰平、つまり平和を実現した人物です。
応仁の乱から【123年】も続いた戦国時代に疲れ果てた全国民を、家康は平和によって癒やし、守ったと言って良いでしょう。
平和によって最も多くの人間を喜ばせた徳川家康とその末裔が、もっとも大きく栄えたと言って良いはずです。
家康は、平和を実現することを、何よりも大切にしていました。
厭離穢土 欣求浄土
この【厭離穢土・欣求浄土】という言葉は、徳川家康が旗印とした言葉です。
地獄のようなこの世を、極楽浄土に変えていこう
というスローガンです。
家康はこの理想を実現したのです。
このスローガン・旗印は、家康が難敵・一向一揆を相手にしたとき、敵がかかげていた旗印に対抗するためにつくったものでした。
進めば往生極楽・退けば無限地獄
前に進んで戦い死ねば極楽へ行ける。
ただし、逃げれば逃れられない無限の地獄へ落ちる、という意味です。
家康はおそらく、この一向一揆の旗印を見て激怒したのでしょう。
救われるためには死んで極楽浄土へ行くしかないという一向一揆の考え方を真っ向から否定し、この世を戦乱の地獄から救い、平和な極楽浄土へと変えよう、と呼びかけたかったのではないでしょうか。
家康は、天下万民の幸福を第一として考えたのです。
織田信長や豊臣秀吉は、外国への出兵を目論んでいました。
それだけではなく、今も昔も、政治を独占し、権力を握っている為政者・政治家と呼ばれる人たちは、自分にとって都合の良い政治を行い、自分が贅沢な生活をしたいという欲望を満たしているものです。
現在日本を統治している自民党・公明党も、増税で民衆からお金を搾り取り、日本史上でも考えられないほどの高い税率を課しています。
(2022年、日本の実質的な税率⦅国民負担率⦆は48%であり、江戸時代の40%より高い)
藤原道長は、摂関政治という方法で政治を独占し
この世は私のための世だ
というほど栄華を極めました。
白河法皇は、院政という政治のやり方で権力を独占し
サイコロと鴨川と山法師以外は、全て私の思うままだ
というほど栄えました。
平清盛たち平家一門は、武力と財力と婚姻政策で政治と権力を独占し
平家一門でないものは人ではない
というほどにおごりました。
それに対して徳川家康の生活は、極めて質素だったといいます。
お手洗いで使用する豪華な便器を商人からプレゼントされたとき、あまりにも豪華だったため激怒して破壊したというエピソードは有名です。
そして家康は、平和をもっとも大切としたのです。
他人(万民)の幸福を最も大切にした
これこそが、家康のもっともすごいところなのではないでしょうか。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 徳川家康は我慢強い人だった。その忍耐力で、数々の苦難を乗り越えて、最期には天下を取ることに成功した。
- 家康は、織田信長や武田信玄の失敗や、自分自身の失敗からも学び、同じ失敗を繰り返さないように、改善を繰り返していた
- 家康は厭離穢土・欣求浄土というスローガンの通り、他人の幸福を最も大切なものとしていた。最後には天下取りに成功し、平和な時代を作り上げることに成功した。
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。
よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました。
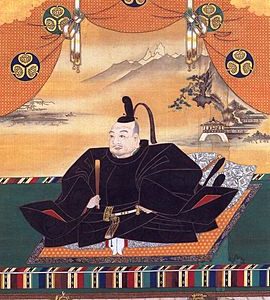

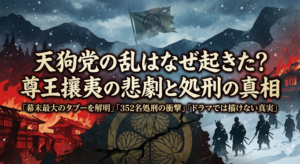
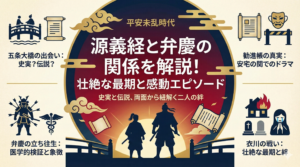
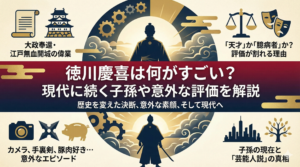
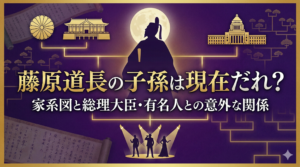

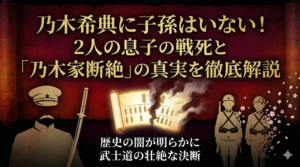

コメント