1336~1392年、「足利尊氏」が生きた「室町時代」と重なる「南北朝時代」について、わかりやすく解説いたします。
南北朝時代とは、どういう時代だったのか?
南北朝時代は、その特徴から「タブー(触れてはいけないもの)」とされていました。
なぜ「タブー」だったのか・・・。
「南北朝時代」は、「2人の天皇」がいた時代です。
長く「ニセ者」とされていた「天皇」が、実は「本物」だったため、「タブー」となってしまったのです
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
- 「南北朝時代」とは、京都に「北朝」、吉野に「南朝」と、「2つの朝廷」「2人の天皇」が存在していた時代。西暦「1336~1392」年のこと。
- 明治44年(1911年)2月22日、明治政府は「南朝」を正統と決めた。明治天皇は北朝の末裔だったため、「南北朝時代」はタブーとされた。
- 南北朝時代の「北朝」の天皇達、「光厳天皇」「光明天皇」「崇光天皇」「後光厳天皇」「後円融天皇」は、歴代天皇にかぞえられていない
南北朝時代とは何かを、超わかりやすく解説!『2人の天皇』がいた時代
「南北朝時代」と呼ばれる理由
「南北朝時代」・・。
なぜ「南北朝時代」と呼ばれているのでしょうか?
『1336~1392年』の「約57年」の間、「朝廷」が北と南に2つ存在していたため、「南北朝時代」と呼ばれています。
現在の「京都市」に北の朝廷「北朝」が。
現在の「奈良県吉野町」に南の朝廷「南朝」があったのです。
なぜ「南北朝時代」は始まったのか?
南北朝時代が始まった理由は、「後醍醐天皇」と「足利尊氏」の対立が原因です。

後醍醐天皇
引用元ウィキペディアより
後醍醐天皇と足利尊氏は「鎌倉幕府」を滅ぼした人物です。

足利尊氏
引用元ウィキペディアより
鎌倉幕府を滅ぼした「後醍醐天皇」は「建武の新政」という、新しい政治を開始。
しかし「建武の新政」で後醍醐天皇は、「足利尊氏」ら「武士」達にたいして、壮絶な「差別」をしてしまうのです。
それに激怒した「武士」達は、「足利尊氏」をリーダーにして、「後醍醐天皇」に戦いを挑むこととなります。
戦いは「足利尊氏」が勝利します。
名将「楠木正成」がひきいた「後醍醐天皇」の軍を「湊川の戦い」で倒した足利尊氏は、後醍醐天皇を「退位」させるのです。
新しく「天皇」の位についたのは、後醍醐天皇と仲が悪かった「光明天皇」。
後醍醐天皇は、足利尊氏の手で幽閉されてしまいます。
しかし、絶対にあきらめない性格の「後醍醐天皇」は、幽閉先から女装して脱獄。
京都から「吉野」へ移動し、そこに新しい「朝廷」をつくり、みずから「天皇」を自称するのでした。
これが「南の朝廷」・・「南朝」の成立です。
京都にいた「光明天皇」に対して、南に「後醍醐天皇」が登場。
1336年、「南北朝時代」「南北朝の動乱」が始まったのです。。
「朝廷とは何なのか」については、以下のリンク記事を、ぜひ役立てくださいませ。
なぜ南北朝時代は「タブー」とされたのか?明治維新の真実
この「南北朝時代」は、「明治維新」のあたりから、長く「タブー(触れてはいけないもの)」とされてきました。
なぜなのでしょうか?
「明治維新」は「明治天皇」が、長く続いた武家政権「徳川幕府」を倒した事件です。
「明治維新」後、「明治天皇」が即位。
それまで「武士」が支配していた日本のトップに、「天皇」が君臨することとなったのです。
日本を支配する「天皇」は、当然「正統な血筋の天皇」でなくてはいけません。
もしも「天皇」が「ニセモノ」であったら、「明治天皇」は「日本を支配する資格のない者」となってしまうのです。
そうなると「徳川幕府を倒した」ことも、「ただの戦争犯罪」とみなされかねません。
さて、実はその「明治天皇」が、もしかしたら「正統な天皇ではない」のではないか?と疑われてしまう事態が発生します。
それはどういうことなのか・・・。
それを知るためには、「南北朝時代の終わり」について解説しないといけません。
南北朝時代は、1392年、室町幕府の3代将軍「足利義満」の活躍で終わります。
南朝の「後亀山天皇」が、北朝の「後小松天皇」に天皇の位をゆずる形で、「南朝と北朝が合体」するのです。(南北朝合一)
これにより、南北朝時代は終了。
後醍醐天皇がはじめた「南朝」は終わり、「北朝」がその後も天皇を続けることになります。
しかし、この時代「2人の天皇がいた」という異常事態について、のちの「明治政府」は驚くべき決定をするのです。
1911年(明治44年)2月22日、大日本帝国議会は、「南朝」こそが「正統な天皇」であると決議したのでした。
南朝・・・つまり「後醍醐天皇」から「後亀山天皇」までの「4人の天皇」が「正統な天皇」であると明治政府は認めたのです。
北朝の天皇たちは、「正統な天皇」ではない・・と・・・。
明治天皇は「北朝の天皇」の末裔でした。
そのため、「正統な天皇」である「南朝」の末裔ではない「明治天皇」の正統性が、疑われることとなってしまう。
「明治天皇」が正統な天皇ではない・・・そんなことになったら、日本は戦乱の時代をむかえるかもしれません。
それを恐れた人々が、「南北朝時代」をタブー視するようになったのです。
とはいえ、南北朝が終わった後の北朝の天皇は、南朝の「後亀山天皇」から「三種の神器」を継承して即位しているため、それ以後の正統性を保たれているといわれています。
つまり現在の天皇陛下は、「南朝」から「三種の神器」を継承して即位した「北朝」の天皇の末裔であるから、正統性が保たれているとされています。
歴代天皇に数えられない「北朝」5人の天皇たち
南北朝時代・・・この時代「北朝」は「5人の天皇」が存在し、「南朝」には「4人の天皇」がいました。
北朝の5人の天皇とは
1,光厳天皇
2,光明天皇
3,崇光天皇
4,後光厳天皇
5,後円融天皇
この「後円融天皇」の次が、南北朝時代を終わらせた「後小松天皇」です。
南朝の4人の天皇とは
1,後醍醐天皇
2,後村上天皇
3,長慶天皇
4,後亀山天皇
先ほど申しましたとおり、「北朝の天皇は正統ではない」とされているので、「歴代天皇」に数えられないのです。
96代「後醍醐天皇」
97代「後村上天皇」
98代「長慶天皇」
99代「後亀山天皇」
そしてこの次「100代目」が、さきほど解説したとおり、南北朝を終わらせた北朝の「後小松天皇」なのです。
北朝の「光厳天皇」から「後円融天皇」は、「歴代天皇」には数えられていません。
「後小松天皇」も含めて「北朝初代~北朝6代」と呼ばれています。
後小松天皇は「100代目」の天皇であると同時に、「北朝6代目」の天皇でもあるのです。
南北朝時代の「2つの元号」
現在、日本では「令和」という元号が使われています。
しかし南北朝時代には、「2つの元号」が存在していました。
「元号」は、天皇が「時間を支配する」という意味があるため、南北朝それぞれが、「元号」を主張したのです。
北朝の元号は、18個
「正慶」「建武」「暦応」「康永」「貞和」「観応」「文和」「延文」「康安」「貞治」「応安」「永和」「康暦」「永徳」「至徳」「嘉慶」「康応」「明徳」
南朝の元号は、10個
「元弘」「建武」「延元」「興国」「正平」「建徳」「文中」「天授」「弘和」「元中」
この2つの元号は、最終的に「南北朝合一」によって、北朝の元号「明徳」に統一されることとなります。
元号「令和(れいわ)」について、その意味や由来をわかりやすく解説いたします。よろしければ以下のリンク記事をお役立てくださいませ。
南北朝時代と大日本帝国の矛盾
かつての大日本帝国時代、南北朝時代は微妙な扱いを受けていました
それは、天皇家にとって都合の悪い側面があったからです。
南北朝時代は、天皇と武家が権力争いを繰り広げた時期であり、天皇側が敗北したことで、武家政権が続く時代が到来する時代です。
しかし、明治維新は武家政治を否定し、天皇を中心とした国家体制を築きました。
そのため、天皇が敗北したという南北朝時代は、明治の新体制の正当性を揺るがす存在となったのです。
天皇は絶対的な存在であり、歴史上つねに正義であり勝利する側でなくてはいけませんでしたが、南北朝時代に後醍醐天皇は足利尊氏に敗北していたのです。
さらに、南北朝時代には皇室が二つ存在したため、「万世一系」すなわち「日本が誕生してから2600年以上一度も滅びたりしたことのない一つの家系が天皇として支配する国」という、皇室の歴史観にも矛盾が生じます。
そのうえ、正統とされたはずの南朝は皇統から弾かれ、北朝の子孫が明治天皇です。
そのため、大日本帝国時代は、南朝に味方した楠木正成や新田義貞を英雄とし、後醍醐天皇に敵対した足利尊氏を悪人として単純に区別して人々に浸透させていた都合の悪い当時の歴史を隠蔽しようとしたのです。
しかし、歴史は単純な善悪で語れるものではありません。
長い歴史の中で、愚かな天皇も存在したことは事実であり、それは帝国憲法の「万世一系」という理念にも矛盾を生じさせます。
このように、南北朝時代は帝国時代にとって都合の悪い存在であり、歴史認識に歪みを生み出す要因となったわけです。。
南北朝時代についてひとこと言いたい
南北朝時代、この時代は、「南朝」と「北朝」による「戦乱の時代」でした。
「南北朝の動乱」などと呼ばれ、とても厳しい時代であったと考えられます。
そもそもどうしてこの南北朝の動乱が始まったのか?
原因は「後醍醐天皇」の「政治の失敗」です。
後醍醐天皇は、「建武の新政」と呼ばれる「天皇の独裁政治」を開始します。
これは、「武士」という、それまで日本を支配していた者たちを排除し、天皇と公家が日本を支配する政治でした。
例えて言うなら、現代日本において「これから武士たちによる『幕府』という独裁政治を始める」ようなもの。
そんなもの、現代日本で成功するはずがありません。
後醍醐天皇は、それを本気で始めようとしたのです。
武士たちは次々と利権や特権を失い、挙句の果てには「土地」まで強引に奪われ、生活することができなくなっていきます。
激怒した「武士たち」は、「足利尊氏」を担ぎ出して、後醍醐天皇と戦い勝利。
「室町幕府」という、「武士たちによる、武士たちのための政府」を作ることに成功するのでした。
もしも、後醍醐天皇の政治が、もっと真っ当なものであったら、「南北朝の動乱」や、「応仁の乱」、そしてそれに続く「戦国時代」という戦乱の時代は、なかったかもしれません。
政治力のなかった「後醍醐天皇」の独裁・・・。
いつの時代でも、「政治能力の乏しい独裁」は、悲劇を生むということでしょうね。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 南北朝時代とは、1336年~1392年までの約57年間、北と南に「2つの朝廷」「2人の天皇」が存在していた時代のこと
- 1911年(明治44年)2月22日、明治政府は「南朝」を正統とした。そのため北朝の末裔であった「明治天皇」の正統性に疑義が生まれ、「南北朝時代」はタブーとされた
- 南北朝時代の「北朝の天皇」たち、「光厳天皇」「光明天皇」「崇光天皇」「後光厳天皇」「後円融天皇」は、歴代天皇にかぞえられていない
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
よろしければ以下のリンク記事も、お役立てくださいませ。
「足利尊氏の家系図と子孫を調査!性格が良かったため将軍になれた?」の記事はコチラ
「二条城を建てた人は誰?その「歴史」と「天守閣の秘密」を簡単解説」の記事はコチラ
「楠木正成の銅像が皇居にある理由を簡単解説!子孫の苗字と家系図とは」の記事はコチラ


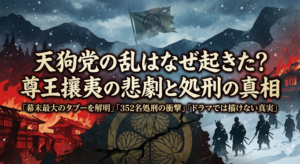
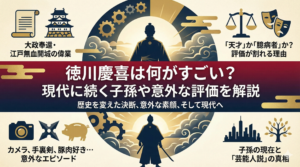
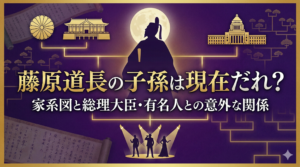

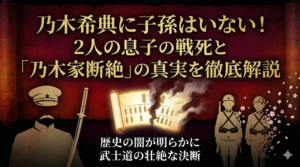

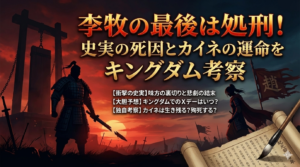
コメント