織田信長と豊臣秀吉と徳川家康の関係をわかりやすく解説いたします。
三人の人柄と性格を、エピソード付きで簡単に解説いたします。
3人は、主君と部下、幼馴染で同盟者、義理の兄弟という関係だったのです。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
- 【信長と秀吉】は主君と部下、【信長と家康】は幼馴染で同盟者、【秀吉と家康】は義理の兄弟、という関係だった
- 【織田信長】は、マキャベリスト(目的のために手段を選ばない人)であるが、その反面とても人情味のある人物
- 【豊臣秀吉】は、人たらしと呼ばれるお祭り男。大物を装っているが、実は器量の狭さも垣間見える
- 【徳川家康】は、温厚だと言われているが、実は短気で神経質。その反面で、豪快さもあわせ持つ
織田信長と豊臣秀吉と徳川家康の関係をわかりやすく解説
三英傑と呼ばれた、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の関係は、とても複雑です。
この三人はそれぞれに
- 【信長と秀吉】は、主君と部下
- 【信長と家康】は、幼馴染で同盟者
- 【秀吉と家康】は、義理の兄弟
という関係でした。
織田信長と豊臣秀吉の関係は【主君と部下】
織田信長と豊臣秀吉は、ひとことでいえば、主君と部下という関係です。
信長にとって秀吉は、たくさんいる部下たちの中でも、特に優秀な部下でした。
信長は、明智光秀と羽柴秀吉という、特に優秀な2人の部下を、何より気に入っていました。
秀吉は織田家のなかでも、明智光秀に次ぐ、とてつもなく優秀な部下だったのです。
織田信長と徳川家康の関係は【幼馴染で同盟者】
織田信長と徳川家康は、ひとことでいってしまうと、同盟者という関係です。
同盟者であると同時に、2人は幼馴染だったといわれています。
幼い徳川家康が、織田家に人質として預けられていたことがあるのです。
2人は成長し、1560年の桶狭間の戦いで今川義元が亡くなったことをきっかけに、同盟を締結します。
1562年、清州城という織田信長の居城で結ばれたこの同盟は、清州同盟と呼ばれています。
裏切りが当たり前だった戦国時代してはめずらしく、信長が亡くなる1582年まで、締結から20年も守られ続けました。
この同盟のおかげで、織田信長は天下統一に向けて、大きく飛躍することができたのです。
豊臣秀吉と徳川家康の関係は【義理の兄弟】
豊臣秀吉と徳川家康の関係は、義理の兄弟でした。秀吉の妹が、家康の妻になっているからです。
秀吉と家康の関係は、移り変わりが激しいので、とても複雑です。
もともとは秀吉よりも、家康のほうが立場は上でした。
なぜなら家康は、秀吉の主君である織田信長と、対等な同盟者だったからです。
例えていうならば、秀吉にとって家康は、自分が務めている会社の社長(織田信長)が仲良くしている、提携先の社長といったところでしょうか。
その後、家康は信長と対等な同盟者から、信長の部下へと格下げになっています。
これで秀吉と家康は、ほぼ対等な同僚になりました。
しかし、本能寺の変で信長が明智光秀に討たれると、立場が変わります。
明智光秀を討伐した秀吉は、信長の後継者となって、一気に天下統一を目指すことになります。
家康は、そんな天下を目指す秀吉の、最大のライバルとなるのです。
しかし家康は、圧倒的な勢いをもつ豊臣秀吉に降参します。
こうして家康は、秀吉の部下となるのです。
このとき、秀吉は自分の妹・旭姫を、家康の妻として嫁がせています。

朝日姫(旭姫)
引用元Wikipediaより
こうして秀吉と家康は、義理の兄弟となって関係を深めたのです。
秀吉と家康の関係の移り変わりは、以下の通りの順に変化していっているのです
- 【秀吉】信長の部下、【家康】信長の同盟者
- 【秀吉】信長の部下、【家康】信長の部下
- 【秀吉】天下を目指す大名、【家康】東海地方の大大名
- 【秀吉】主君、【家康】部下
- 【秀吉】義理の兄、【家康】義理の弟
しかし家康は、秀吉が亡くなると豊臣家を徐々に弱らせて、最終的には滅ぼしてしまいます。
家康は、秀吉のことを、あまり良く思っていなかったのです。
【織田信長】の人柄・性格とエピソード
「鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス」という俳句で有名な織田信長は、とても冷酷な合理主義者でした。
しかし同時に、心優しいエピソードも残された人物なのです。

織田信長
引用元ウィキペディアより
信長の人柄・性格は【冷徹な合理主義者】
織田信長は、冷徹なる合理主義者です。
しかし同時に心優しい一面も持っている不思議な人物です。
信長は、【比叡山・延暦寺焼き討ち】や【長島一向一揆に対する虐殺】などを実行しています。
つまり信長は、とても残忍な性格をしていると考えられています。
ところが日常では、とても心優しいところをみせているのです。
例えば秀吉に対して
「妻を大切にせよ」
と諭したりと、秀吉の妻である【おね】さんを気づかう様子をみせています。
それだけではなく、信長は自分の娘たちを政略結婚の道具にはしていないのです。
娘たちの大半を自分の家臣に嫁がせて、すぐそばに置いておこうとしています。
例えば、部下の前田利家の息子・利長に、自分の娘を嫁がせています。
これらを見て考えてみると、信長の人間味ある様子がうかがえます。
ただし、信長が合理主義者で、現実主義者であることは確かです。
自らの目で見たものしか信じず、しかもあらゆる手を駆使して目的を達成する人物です。
信長は現代でいうところの【マキャベリスト】であると、よくいわれます。
マキャベリストとは、つまり【目的のために手段を選ばない人のこと】です。
エピソード❶池に龍が住んでいると聞いて自ら確認した
信長には、【龍が住んでいると噂される池に自分で潜って龍がいないことを確認した】、という現実主義者であることを物語るエピソードが残っています。
信長がまだ、尾張の国の領主であった頃の話です。
領内の池に龍が住んでいるという噂が広まり、信長はこの池を視察に来ました。
すると信長は、池に龍がいるかどうか確かめてくると言い出したのです。
信長はたった一人で水中へ潜っていきました。(信長は水泳が得意だった)
何度も何度も潜り続けて、龍を探し続けた信長でしたが、結局龍は見つかりませんでした。
そして信長は
「龍なんかいないじゃないか!」
と激怒すると、ありもしない噂を広めてはいけないと、いわゆる【風説の流布】を禁じて帰ったのでした。
エピソード❷領民に危害を加える兵士は即処刑
信長は、女性をからかう織田家の兵士を、即座に斬り捨てたといいます。
これは、ヨーロッパから来たキリスト教の宣教師ルイス・フロイスが、初めて信長と会った時の話です。
信長は当時、征夷大将軍となった足利義昭を住まわせる為の京都・二条城を建築士、自ら工事を指揮していました。
その建築現場に、笠をかぶって歩く若い女性の顔をのぞき込んだり、笠をめくりあげてからかう兵士が、信長の目につきました。
一直線に兵士の元へ走っていった信長は、なんと問答無用でその兵士を斬り捨てたのでした。
織田軍団には、領民に危害を加える者は処刑するという法があったのです。
信長は女性をからかう兵士が、その法律を破ったとみなして、その罪で即処刑したのです。
これを見ていたルイス・フロイスはとても驚き、このエピソードを、記録に残したのでした。
エピソード❸昼寝する領民を処刑した信玄の父と、許した信長
出陣する領主を見送らずに、昼寝していた農民を、武田信玄の父親は処刑し、織田信長は笑って喜んだという逸話があります。
武田信玄の父・武田信虎は、出陣する際に農道で昼寝している農民を発見し、礼をしなかったその農民を処刑したといわれています。
それに対して信長は、同じく出陣の際に昼寝する農民を見つけて激怒する部下たちをなだめて、こう言ったそうです。
「俺はあんな光景が好きだ。
ああいう光景を日常のものとするためにも、早く平和な世を築こう」
武田信虎はその後、あまりにも無能であったため、息子の武田信玄から追放されたのでした。
【豊臣秀吉】の人柄・性格とエピソード
「鳴かぬなら 鳴かせてみしょう ホトトギス」という俳句で有名な豊臣秀吉は、【人たらし】と呼ばれるほど、人心掌握術の天才でした。
派手付きで賢いけれど、プライドが高くて、人を許せる度量がせまい、とても怒りっぽい人です。
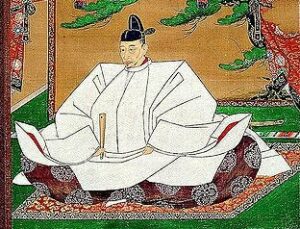
豊臣秀吉
引用元ウィキペディアより
豊臣秀吉の人柄・性格は【派手好きな人たらし】
豊臣秀吉は、派手好きなお祭り男で、人の心をつかむのが上手でしたが、器が小さく、怒らせると何をするかわからない人でもありました。
秀吉は人を楽しませることにおいては天下一、と言っても言いすぎではない「人たらし」です。
度胸があり、ある程度は人を許せる度量の広さもあるものの、小心者な側面もある人です。
処世術に長けており、気難しい信長とうまく付き合ったことでも有名です。
天下人となった後、それまで調整役であった弟・豊臣秀長を病気で亡くしてしまいます。
相談相手でもあった弟を亡くした頃から、秀吉は徐々におかしくなっていきます。
朝鮮出兵という無謀な戦争を始めたり、甥・豊臣秀次を無実の罪で処刑してしまうなど、自らの首を絞める行為を繰り返すようになるのです。
エピソード❶鶴を逃した家臣を許す
秀吉には、自分が飼っていた鶴を逃してしまった部下を優しく許した、というエピソードがあります。
秀吉が大切にしていた鶴を、家臣の一人が逃してしまった時のことです。
家臣は死罪を覚悟で、正直に秀吉に告白し、謝罪したのでした。
すると秀吉は笑ってひとこと、こう言いました。
「どこに逃げても、日本は私の庭だ。気にするな」
「日本は私の庭だ」と、天下統一を成功させた支配者の余裕がうかがえるエピソードです。
エピソード❷人材コレクターだった
豊臣秀吉は優秀な若武者を好み、能力のある人材を追い求めること人一倍だったといわれています。
秀吉は、半分農民だった下級の足軽【木下弥右衛門】の息子でした。
そのため他の武将たちと違って、【譜代の家臣団】つまり、親から引き継いだ部下たちを持っていないのです。
それが原因だと思いますが、秀吉は人材を育成したり、集めたりすることにとても熱心です。
福島正則や加藤清正など、自分の親戚から優秀な若者を引き取って、武将として育てました。
自分の軍師・黒田官兵衛孝高の息子・黒田長政の命を救って育ててもいます。
さらには寺の小僧だった石田三成をスカウトし、官僚として育て上げます。
大谷吉継や、その娘婿・真田信繁(別名・幸村)のような若者も、小姓として採用しています。
家康の次男で秀吉の養子となった結城秀康は、実の父・徳川家康から嫌われた反面、養父であった秀吉にかわいがられ、秀吉に忠誠を誓っていたといわれています。
「(秀吉の息子)豊臣秀頼様に何かあったら、俺は真っ先に大坂城に駆けつける」
と結城秀康は、宣言するほど、秀吉に感謝していたようです。
晩年まで子宝に恵まれなかった秀吉は、その反面、子供や若者に優しかったといわれています。
エピソード❸落書きに激怒して門番に八つ当たり
秀吉は、側室の淀殿とのあいだに生まれた自分の子供が、「淀殿が別の男と浮気して生まれた子だ」という悪口を屋敷の壁に落書きされ、激怒して門番を処刑しています。
秀吉は、自らの器量の大きさをアピールするものの、プライドが高く、自分を軽くあつかう者に対しては、残酷に処刑することも少なくありませんでした。
聚楽第の壁に、「産まれたお前の子は、妻と不倫相手の子供だ」と悪口を落書きされた時、激怒。
犯人を探したものの見つからなかったため、八つ当たりのように、その屋敷の門番をかなり残酷な処刑をしたといわれています。
実は秀吉は、人を許す器がそれほど大きかったわけではなく、大きいふりをしていただけなのかもしれません。
【徳川家康】の人柄・性格とエピソード
「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」で有名な徳川家康は、とても短期でしたたかな人物だったと考えらえます。
最後に天下を取った【海道一の弓取り】と呼ばれた徳川家康について解説いたします。

徳川家康
引用元ウィキペディアより
徳川家康の人柄・性格は【短気なしたたか者】
徳川家康は、非常に忍耐強くて温厚だったといわれていますが、実はかなり短気で神経質だったといわれています。
信長にはこき使われ、秀吉には故郷の領地・三河を取り上げられて関東へ追い出されています。
それでも忠実なふりを続けて絶好のタイミングをまち、信長が死んだ直後には「天正壬午の乱」と呼ばれる「信濃・甲斐」の争奪戦を勝ち抜いて飛躍。
更に秀吉の死後には、法律として定められていた「大名同士での婚姻は、届出が必要」という法を破って縁組をしまくったため、詰問されるとサラリと一言
「コロッとわすれていた」
また大坂の陣で、和睦条件の「外堀の埋めたて」を破り、外堀だけではなく内堀も埋めてしまい抗議されると
「うっかりしてた」
と一言。
後世で「たぬきおやじ」と揶揄されるのも納得できる狡猾さです。
人の思惑通りには動かない、つまりは【したたか者】という印象を持ちます。
実は口数が少なく、部下達から「何を考えているのかわからない」といわれていたようです。
慎重な性格で、言葉を慎重に選んでいたのでしょう。
エピソード❶今川義元の目の前で堂々と用を済ませる
幼い頃の家康は、主君だった今川義元の目の前で、堂々と用を済ませて、周囲を驚かせたという逸話があります。
家康が幼いころのことです。
人質として預けられていた今川家で、当主の今川義元に謁見する機会がありました。
その時、幼い家康は、何を思ったのか対面が終わると、庭先で突然放尿をし始めたのです。
それを見た今川義元は、怒るかと思いきや、こう言って褒めたといいます。
「肝に毛が生えた子供だ」
子供の頃の家康は、とても大胆不敵な子だったようです。
エピソード❷激怒して旗を切り倒す
天下分け目の関ヶ原の戦いで、温厚と言われていた家康は、部下に馬をぶつけられて激怒し、旗を斬り倒して八つ当たりしたといいます。
温厚な性格であるといわれている徳川家康ですが、そんなことはないようです。
家康は、非常に激しい性格をしていたと考えられます。
1600年、関ヶ原の戦いにおいて、事件は起こりました。
使番の馬が自分の馬にぶつかって、そのまま走り去っていってしまいました。
激怒した家康は刀を抜いて、近くにあった旗を切り倒して八つ当たりしたのでした。
このシーンは、2000年の大河ドラマ「葵〜徳川三代〜」の第一話で描かれています。
徳川家康は相当に短気で、使用していた軍配の手元は、歯型でいっぱいだったのだとか。
しかも家康は神経質で、爪を噛む癖があったといわれています。
エピソード❸豊臣秀吉に陣羽織をねだった
徳川家康は、かなり大胆な性格だったらしく、大坂城で豊臣秀吉にあいさつをしたとき、秀吉の陣羽織が欲しいと言い出したそうです。
この理由について家康は、こう言ったそうです
「関白殿下(秀吉)に、戦でつかう陣羽織は、二度と着せません。
殿下の戦は、すべてこの家康が代わりにいたします」
そもそも主君に物をねだる行為は、あまりに非礼です。
この言葉の裏には、家康なりの挑戦の意味があったのではないでしょうか。
「武家ではなく、お公家さんの官位である関白になった秀吉に、もはや武士の代物である陣羽織は無用。
今後、武家の棟梁は、この家康が代わりにつとめます。」
もしかすると、こんな隠れた挑戦的な真意があったのかもしれません。
また、家康は実の息子である松平信康を処刑するという、とても厳格な一面も見せています。
温厚というのは、後世の人々の勝手な思い込みかもしれません
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 【信長と秀吉】は主君と部下、【信長と家康】は幼馴染で同盟者、【秀吉と家康】は義理の兄弟、という関係だった
- 【織田信長】は、マキャベリスト(目的のために手段を選ばない人)であるが、その反面とても人情味のある人物
- 【豊臣秀吉】は、人たらしと呼ばれるお祭り男。大物を装っているが、実は器量の狭さも垣間見える
- 【徳川家康】は、温厚だと言われているが、実は短気で神経質。その反面で、豪快さもあわせ持つ
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
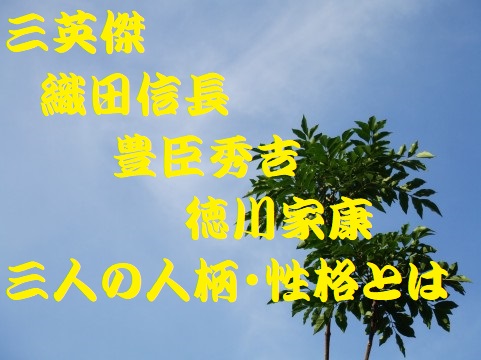

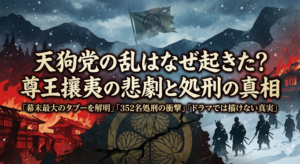
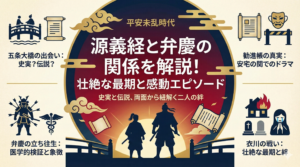
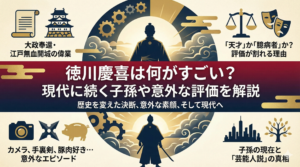
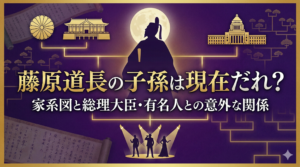

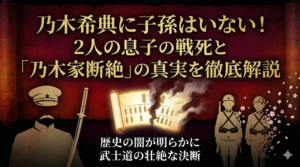

コメント
コメント一覧 (2件)
[…] と、信長の性格はサイコパス、合理的、現実主義者だと言われていたそうです。(出典) […]
[…] レキシル […]