今回のテーマは豊臣秀吉と関白です
この記事では豊臣秀吉が【関白】に就任した理由と征夷大将軍にならなかった理由について、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。
これを読めば秀吉が関白になった理由を、カンタンに理解できます。
秀吉は征夷大将軍ではなく、関白になることで、前人未到の偉業を達成しようとしたのです。または、徳川家康によって征夷大将軍になる道を阻止されてしまったという意見もあるようです
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
1,豊臣秀吉が関白に就任した経緯・流れとは?
【1582年】、織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれる。
【1583年】、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を倒し、織田家を乗っ取る。
【1585年】、秀吉が関白に就任。
2,秀吉は、なぜ関白になれたのか?
秀吉は、元関白である近衛前久の養子となることで、五摂家しか就任できないはずの関白に就任した。
3,秀吉が征夷大将軍になれなかった理由とは?
当時はまだ征夷大将軍の職に足利義昭が就いていたので、征夷大将軍の職が埋まっていた。だから秀吉は将軍になれなかった。
豊臣秀吉が関白に就任した経緯や流れ!そもそも関白って何?
天下統一をなしとげた偉人・豊臣秀吉は、【1585年】、関白という役職に就任しています。
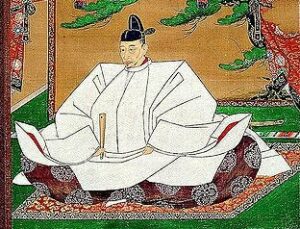
《豊臣秀吉》
「引用元ウィキペディアより」
豊臣秀吉が関白に就任するまでの流れを、ザッと年表にすると、以下のとおりです。
秀吉の関白就任までの年表
【1582年6月】、羽柴秀吉の主君である織田信長が、本能寺の変によって、重臣・明智光秀に討たれて戦死。
その後、羽柴秀吉は明智光秀を討ち果たし、信長の後継者としての地位を確立して天下統一へと進むことになるのです。
【1583年】、賤ヶ岳の戦いで、ライバル柴田勝家を倒し、羽柴秀吉は織田家という日本最大の勢力を乗っ取ることに成功。
【1584年】、ライバル徳川家康と小牧・長久手の戦いで激突。
【1585年】、四国の大名・長宗我部元親を倒すため、四国征伐を弟・羽柴秀長と軍師・黒田官兵衛に指示。
【1585年】、羽柴秀吉が関白に就任。
【1586年】、羽柴秀吉は、天皇から豊臣の氏を与えられ、豊臣秀吉と名乗る。
関白とは何か?
関白とは、天皇にかわって政治をおこなう最高位の役職です。
朝廷という政府のなかで、関白は天皇に次ぐ最高の位なのです。
この時代から、すでに天皇は、自ら政治を行う存在ではありませんでした。
そのため、関白や征夷大将軍が、代わりに政治を行なっていたのです。
天皇のかわりに政治を行う役職。それが関白
つまり関白は、まさに天下で最高の地位というわけです。
さて、ここで一つの疑問がわいてきます。
なぜ農民出身の秀吉は、天下で最高の地位である関白に就任できたのでしょうか?
軍事力や財力を持っているだけでは、関白にはなれません。
たとえ天下を統一した農民である秀吉であっても、それは変わりません。
そもそも関白とは、代々五摂家と呼ばれる5つの摂関家という名門公家が、交代で就任していた位です。
つまり五摂家以外の人間が、関白に就任することは、そもそも不可能だったのです。
なぜ、秀吉は関白になれたのか。
その理由は、秀吉が関白の位をだまし取ったからです
ちなみに五摂家とは、紫式部と同じ時代を生きた権力者・藤原道長の子孫である5つの家
- 近衛家
- 鷹司家
- 一条家
- 二条家
- 九条家
の5つの家のことです。
→→→→→【秀吉の天下統一までの道のり】についてくわしくはこちら
農民・秀吉は、なぜ最高位・関白になれたのか?
農民であった秀吉は、元関白・近衛前久の養子となって、近衛家の人間になることで、関白に就任しました。
そもそも天下を支配するためには、それにふさわしい官位・身分が必要となります。
そうでなくては、天下を支配する権利を主張することが出来ず、誰も秀吉の命令に従わないからです。
天下統一のためにも、秀吉には関白または征夷大将軍という地位が必要でした。
実は秀吉、巧妙に関白職をだまし取っているのです。
二条昭実と近衛信尹という2人のお公家さんが争いを起こしたところに、秀吉は上手につけこんだのです。
秀吉が関白に就任する直前、朝廷の中でこの二人が、次の関白職をめぐって争っていました。
秀吉は、この争いを終わらせるためと言って、どちらにも軍配を挙げず自らが、二条昭実と争っていた近衛信尹の父親・近衛前久の養子になって関白に就任します。
二人の争いが激化するのを防ぎ、さらに関白の地位がいつまでも決まらないことを防ぐための臨時の措置でした。
このときの秀吉による関白就任は、あくまでも二条昭実と近衛信尹が次の関白となるためのあいだをつなぐ臨時の措置だったはずなのです。
【1591年】、秀吉は関白の職を、二条昭実でも近衛信尹でもなく、甥である豊臣秀次にゆずってしまいます。

《豊臣秀次》
『引用元ウィキペディアより』
つまり秀吉は、関白の職を預かっただけのはずが、自分の血縁者であり後継者である秀次にゆずり、関白の職は、今後豊臣家が代々継承していくことを天下に示してしまったのです。
ここに五摂家が数百年も独占してきた関白の職は、豊臣秀吉によって、だまし取られることになったのでした。
→→→→→【征夷大将軍と関白の違い】についてくわしくはこちら
農民・秀吉が征夷大将軍になれなかった理由
征夷大将軍・足利義昭が秀吉に抵抗したため
豊臣秀吉が征夷大将軍になれなかった理由は、当時の征夷大将軍・足利義昭が、未だに生きており、征夷大将軍の職を手放さなかったからだと考えられます。
征夷大将軍は、全ての武士達のトップの地位です。
全ての武士に命令する権限を持ち、命令に従わないものは、滅ぼされても文句が言えなかったのです。
つまり征夷大将軍の職も、関白と同じく、天下を支配するにふさわしい地位だったのです。
秀吉が関白の職につく12年前の【1573年】、足利義昭は織田信長から追放され、室町幕府は滅亡しています。

《足利義昭》
「引用元ウィキペディアより」
しかし足利義昭はそれ以降も、征夷大将軍の職につき続けていました。
足利義昭が征夷大将軍を続けていたこのとき、征夷大将軍の職に秀吉がつくには、3つの方法がありました。
- 足利義昭が亡くなる
- 義昭自身が征夷大将軍の職を辞める
- 秀吉が足利義昭の養子となって、足利家の人間として将軍職を継承する
しかし足利義昭が、将軍職を辞めることも、秀吉を養子とすることも拒絶。
そして【1597年】まで足利義昭は生きています。(秀吉は、この翌年に亡くなる)
【1587年】、足利義昭は【14年】ぶりに京都へ帰還。
【1588年】、秀吉が関白に就任した3年後、足利義昭はようやく征夷大将軍の職務を辞めています。
このとき、秀吉はすでに関白となって天下を支配する権限を持っていましたから、征夷大将軍の職は不要となっていたのでしょう。
【征夷大将軍は源氏しかなれない】は嘘だった
ちなみに、征夷大将軍には源氏しかなることはできないと言われていますが、この説は正しくないと考えられます。
織田信長は、源氏ではなく平氏であるにも関わらず、征夷大将軍の職務につくことを朝廷と相談しています。
秀吉は源氏でなかったから征夷大将軍になれなかった、という説は、可能性が低いと思います。
ただし、秀吉は征夷大将軍に絶対になれなかったわけではなく、ならなかったとみることもできます。
関白に就任したほうが、歴史に名を刻むことができるからです。
詳しくは、次の項で解説いたします。
征夷大将軍になるよりも、関白になる方が難しかった!
関白になれるのは、五摂家のみだった
秀吉からすれば、征夷大将軍になるよりも関白になるほうが、はるかに難しかったと考えられます。
関白は本来ならば、藤原道長の血を引く五摂家しかなれない役職でした。
しかし征夷大将軍は武士であれば、なれる可能性があるのです。
秀吉は農民出身です。(とはいえ秀吉は半兵半農であり、農民であると同時に武士でもあった)
かつて天下を制した源頼朝や足利尊氏のように、名門出身ではなかった秀吉は、全国の武士から侮られず従えるためにも、高い地位が必要だったのです。

《源頼朝》
「引用元ウィキペディアより」
関白は、天皇の次に位置する最高の位で、征夷大将軍よりも上に位置していました。
実は関白という職は、形式上は
- 源氏
- 平氏
- 藤原氏
- 橘氏
という、4つの氏を名乗るものしか就任できない、とされていたといいます。
しかし秀吉は、これら4つの氏ではなく、新しい氏を欲しがりました。
その新しい氏が豊臣です。
なぜ秀吉は、新しい氏を欲しがったのか?
その理由は、秀吉が天下統一という、それまでだれも成し遂げられなかった偉業を達成したためです。
秀吉は、前人未到の偉業を達成した自分は、歴史上で誰も到達していない地位に就任して当然であると考えていたのです。
だからこそ、秀吉は五摂家以外に就任できない関白を目指したのでしょう。
だれも成し遂げたことのないことを成し遂げることで、秀吉は、天下にその偉業を示そうとしたのです。
関白には五摂家以外はなれない。
その不可能を可能とすることで、秀吉は、天下の全てを従えると同時に、歴史に自らの名前を強烈に刻もうとしたのです。
権力欲が強い秀吉らしい事情です。
ちなみに秀吉は、源頼朝の像に対して
天下を制した私達は、友である。
しかし名門出身のあなたとは違い、私はもっと低い農民という身分の出身だ。
だから私のほうが上だ。
と言ったのだとか。
不遜というか何というか、秀吉らしいセリフです。
秀吉の征夷大将軍就任を阻止したのは徳川家康
歴史家の小和田哲男先生がおっしゃるには、秀吉が征夷大将軍に就任できなかったのは、小牧・長久手の戦いで、秀吉が家康に敗北していたためだとのことです。

《徳川家康》
「引用元ウィキペディアより」
征夷大将軍とは、もともとは京都の東に位置する夷つまりは異民族を討伐するための臨時職でした。
ところが秀吉は、このとき京都の東に位置する三河国(愛知県東部)から駿河(静岡県中部)を支配していた徳川家康に、1584年の【小牧・長久手の戦い】で敗北しているのです。
これは、征夷大将軍という職に期待されている結果とは、矛盾するものです。
東の敵を討伐するはずが、東の敵である徳川家康に敗北しているのですから、当然です。
そのため、朝廷は秀吉に対して、征夷大将軍という職を与えることを渋ったというのが、小和田哲男先生の考えでした。
余談ですが、この小牧・長久手の戦いのあと、徳川家康は秀吉の妹である朝日姫(旭姫)を妻としてむかえ、豊臣政権で一気に飛躍することになります。
→→→→→【朝日姫(旭姫)の最期と死因】についてくわしくはこちら
源頼朝は鎌倉から関東を支配して、関東東北の敵を討伐する名目で、征夷大将軍の職を手に入れました。

《源頼朝》
「引用元ウィキペディアより」
足利尊氏もまた、鎌倉を中心に関東で暴れる敵・北条時行を倒すために、征夷大将軍の職を後醍醐天皇に求めました。

《足利尊氏》
「引用元ウィキペディアより」
ところが秀吉はというと、京都から東に位置していた徳川家康を倒す名目で征夷大将軍を求めたのでしょうけれども、そもそも負けているので、将軍職を与えていいのかと、朝廷が渋るのも無理のない話です
言ってみれば、徳川家康は秀吉の征夷大将軍就任を阻止したともいえるわけです。
小牧・長久手の戦いから19年後の1603年、徳川家康は征夷大将軍に就任。秀吉に奪われそうになった将軍職を、家康は取り返したともいえるかもしれません。
その後、将軍職は徳川家によって世襲され、徳川慶喜まで15代にわたって続くのでした。
→→→→→【足利尊氏の家系図と子孫】についてくわしくはこちら
まとめ
本日の記事をまとめますと
1,豊臣秀吉が関白に就任した経緯・流れは、以下の通り。
【1582年】、織田信長が本能寺の変で明智光秀に討たれる。
【1583年】、賤ヶ岳の戦いで柴田勝家を倒し、織田家を乗っ取る。
【1585年】、秀吉が関白に就任。
2,秀吉は、元関白である近衛前久の養子となることで、五摂家しか就任できないはずの関白に就任した。
3,秀吉が征夷大将軍になれなかった理由は、当時まだ征夷大将軍の職に足利義昭が就いていたので、征夷大将軍の職が埋まっていた。だから秀吉は将軍になれなかった。
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。
よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました
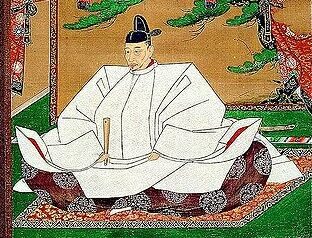
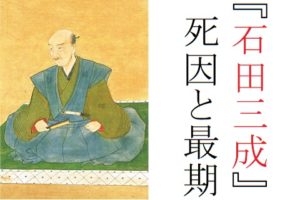

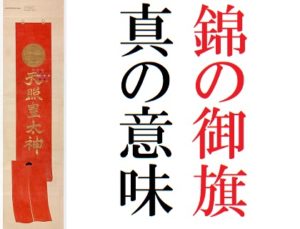




コメント
コメント一覧 (1件)
[…] →→→→→【秀吉が征夷大将軍ではなく、関白になった理由】についてくわしくはこちら […]