薩摩藩士がよく口にしている【チェスト】という言葉。
昔から薩摩人は英語が話せたのか?と思ってしまいますよね。
実はこれ、掛け声がなまってチェストになった、など起源は諸説あるのです。
この記事ではチェストについて調査し、わかりやすく解説いたします。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
- 【チェスト】というのは、薩摩藩で訓練されていた剣術・示現流の掛け声
- この掛け声は、江戸時代後期から使われ始めたという説がある
- 【チェストとは、【知恵を捨てろ】という言葉がなまったもの、とも言われている
【チェスト】ってどういう意味?
チェストとは、どうやら鹿児島の方言で、気合を入れるための掛け声のようなものだそうです。
ドラマや映画などで、薩摩藩士がよく口にする【チェスト】という言葉をご存知でしょうか。
まるで薩摩藩士は英語がしゃべれるのではないか?という印象を与えます。
これにはいったいどういう意味があるのでしょうか?
実は鹿児島県の方言で、自分を鼓舞する時に使う叫び声です。
つまり雄叫び。
戦い前など、気合を入れるために使われていたみたいです
いつからチェストと叫ぶようになった?
はっきりとしたことはわかりませんが、【チェスト】という言葉は江戸後期から使われていると言われています。
その始まりは、剣法の掛け声。
薩摩の剣法は示現流で、薩摩藩を中心に伝わった古流剣術です。
流祖は、戦国時代の剣豪【東郷重位】。
薩摩内では、江戸後期に藩主・島津斉興より御流儀と称され、薩摩藩の一部の分家を除き、藩外の者にこの剣術を教えることは、厳禁とされていました。
この示現流の掛け声の時に【チェスト】が使われていたので、薩摩藩士は気合を入れる時などによく口にしていたみたいです。
掛け声が、なぜよりによって【チェスト】なのか?
英語が使われているように聞こえる掛け声【チェスト】ですが、実は英語ではないようです。
英語が使われていたのではなく、示現流の心構えの一つ【知恵を捨てろ】という言葉がだんだん訛り、【チェスト】になったという説があります。
知恵を捨てろ → ちぇすてよ → チェスト
いろいろな説がありますが、これが有力だと思います。
本来であれば、【エイ】などの掛け声になりそうなものです。
しかし示現流はこのあと解説するように、最初の一撃に全力をつくす剣術であるため、掛け声が【エイ】では、力が入りきらないのかもしれません。
薩摩藩士・示現流について、レビュー(評論)!
この【チェスト】という言葉が、いつから使われていたのか、はっきりとはわかりません。
【チェスト】という言葉、漫画やゲームでは、江戸時代以前から使われていた描写があります。
この記事では江戸時代後期という説を取り上げました。
しかしその根拠がはっきりとしたものではないため、真実は違う可能性もあります。
薩摩示現流は、最初の一太刀に全てを込める、つまり一撃で決めることを目的とした剣術だそうです。
二の太刀要らず、つまり二度目の攻撃を考えてはならない一撃必殺の剣術だったみたいですね。
これはつまり、決死の覚悟で刀を振り下ろせ、ということですね。
薩摩藩が強かった理由の一つがわかった気がします。
まとめ
本日の記事をまとめますと
・チェストというのは、剣術における掛け声
・この言葉が使われ始めたのは江戸後期といわれている
・起源は英語ではなく、知恵を捨てろから訛ったものではないか
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
よろしければ以下のリンク記事も、お役立てくださいませ。
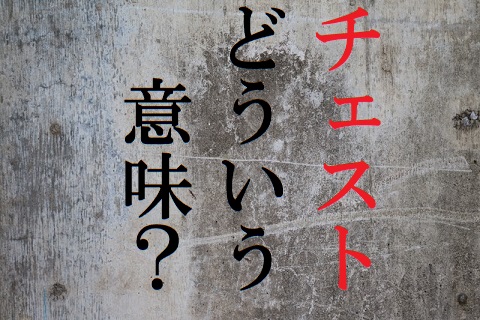
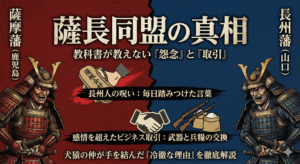
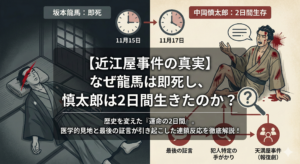

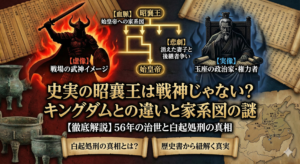
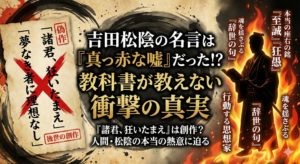

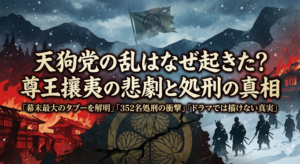
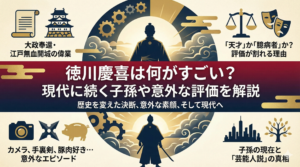
コメント