鎌倉時代に京都に設置された六波羅探題という機関をご存知でしょうか。
歴史の授業で名前を聞いたことがあっても、誰が設置したのか、なぜ置かれたのかまで詳しく知っている方は少ないかもしれません。
六波羅探題は承久の乱という歴史的事件をきっかけに誕生し、鎌倉幕府が全国を統治するための重要な拠点として機能しました。
この記事では、六波羅探題を置いた人物や設置の背景、その役割について初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
歴史の教科書には載っていない興味深いエピソードや、鎌倉幕府がなぜ京都に監視機関を置く必要があったのかという疑問にもお答えします。
- 六波羅探題を設置した人物と承久の乱との関係
- 六波羅探題が置かれた場所と理由
- 六波羅探題の具体的な役割と権限
- 六波羅探題の滅亡とその歴史的影響
六波羅探題を置いたのは誰?設置の背景を徹底解説

| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 設置年 | 1221年(承久3年) |
| 設置者 | 北条義時(鎌倉幕府第2代執権) |
| 設置のきっかけ | 承久の乱での幕府の勝利 |
| 初代北方長官 | 北条泰時(義時の長男) |
| 初代南方長官 | 北条時房(義時の弟) |
| 設置場所 | 京都六波羅(現在の東山区周辺) |
| 滅亡年 | 1333年(元弘3年/正慶2年) |
六波羅探題を設置したのは北条義時と鎌倉幕府
六波羅探題の設置を決定したのは、鎌倉幕府の第2代執権である北条義時です。1221年の承久の乱で後鳥羽上皇率いる朝廷軍を完全に打ち破った北条義時は、再び朝廷が反乱を起こさないよう京都に監視機関を設置する必要性を痛感しました。
北条義時は伊豆の豪族出身で、姉の北条政子が源頼朝の妻となったことで鎌倉幕府の中枢に入りました。父の北条時政が初代執権となり、その後義時が第2代執権として幕府の実権を握ります。承久の乱での勝利により、義時は朝廷を上回る権力を手に入れ、武家政権の基盤を固めることに成功しました。
六波羅探題は鎌倉幕府が西国支配を強化するための出先機関として位置づけられました。初代の北方長官には義時の息子である北条泰時が、南方長官には義時の弟である北条時房が任命され、北条一門の中でも特に信頼の厚い人物が京都に駐留することになりました。
承久の乱が六波羅探題設置のきっかけになった理由
承久の乱は六波羅探題誕生の直接的なきっかけとなった歴史的事件です。1221年5月、後鳥羽上皇は北条義時追討の院宣を発し、全国の武士に対して義時を討つよう命じました。これは朝廷が武家政権に対して武力行使した初めての事例であり、日本史における重大な転換点となりました。
鎌倉時代の初期、朝廷と幕府の関係は比較的良好でした。しかし3代将軍の源実朝が暗殺された後、後鳥羽上皇の皇子を次期将軍に迎える計画が頓挫したことで両者の関係は悪化します。さらに義時が上皇の地頭罷免要求を拒否したことで、緊張関係は決定的となりました。
承久の乱で幕府軍はわずか1ヶ月で朝廷軍を壊滅させました。圧倒的な兵力差と東国武士団の結束力により、幕府は完全勝利を収めます。戦後、北条義時は後鳥羽上皇を隠岐島へ、順徳上皇を佐渡島へ流罪とし、朝廷に味方した貴族や武士の多くを処刑しました。この徹底的な処罰により、朝廷の権威は大きく失墜します。
承久の乱後の幕府の対応
承久の乱での勝利後、鎌倉幕府は朝廷側についた貴族の所領約3,000ヶ所を没収し、これを御家人たちに分配しました。これらの新たに任命された地頭を新補地頭と呼び、西国における幕府の支配基盤を大きく広げることに成功しました。
しかし鎌倉から京都までは約450kmも離れており、情報伝達や緊急時の対応に時間がかかるという問題がありました。そこで北条義時は京都に常設の監視機関を置くことを決断し、これが六波羅探題の誕生につながったのです。
京都守護から六波羅探題へ変わった背景
六波羅探題が設置される前、京都には京都守護という役職がすでに存在していました。京都守護は1185年に北条時政が就任した役職で、主に京都周辺の治安維持を担当していました。
京都守護の設置は文治の勅許と呼ばれる出来事に由来します。源頼朝が平家を滅ぼした後、弟の源義経が後白河法皇に接近して頼朝と対立しました。この際に北条時政が1,000名の騎馬兵を率いて上洛し、後白河法皇に守護・地頭の設置を認めさせたのです。
しかし承久の乱において、京都守護は朝廷側に寝返ってしまいました。この裏切り行為により、京都守護は幕府からの信頼を完全に失い廃止されることになります。六波羅探題は京都守護の機能を引き継ぎつつ、さらに強化された組織として新たに誕生しました。
| 比較項目 | 京都守護 | 六波羅探題 |
|---|---|---|
| 設置年 | 1185年 | 1221年 |
| 主な役割 | 京都の治安維持 | 朝廷監視・西国統治・裁判 |
| 組織構造 | 単独の守護 | 北方と南方の2組織 |
| 管轄範囲 | 京都周辺のみ | 京都および西国全域 |
| 軍事権限 | 限定的 | 独自に軍を動かせる |
| 幕府内の地位 | 中堅役職 | 執権・連署に次ぐ重職 |
六波羅の地が選ばれた理由とは
六波羅という地名は、京都市東山区の松原通から七条通にかけての鴨川東岸一帯を指します。この場所が選ばれたのには明確な理由がありました。
六波羅はかつて平清盛をはじめとする平家一門の屋敷が立ち並んでいた地域で、武家の拠点として歴史があった場所です。平家滅亡後は荒廃していましたが、京都御所に近く朝廷の監視に最適な立地条件を備えていました。
また六波羅は交通の要衝でもありました。東海道や東山道から京都に入る際の玄関口にあたり、東国から上洛する武士たちの動きを把握するにも便利な場所でした。鴨川を挟んで京都の中心部と向き合う位置にあり、何か事態が発生した際にも迅速に対応できる距離感が重視されました。
六波羅という名前の由来
六波羅という地名の由来には諸説あります。仏教用語の六波羅蜜からきているという説や、平安時代に葬送地だったことから六道の辻と呼ばれていた説などがあります。いずれにしても古くから京都の歴史と深く結びついた土地でした。

現在の六波羅探題跡には石碑が建てられており、東福寺近くに六波羅門という史跡も残されています。当時の六波羅には北方と南方の2つの館が建てられ、それぞれに長官が駐在していました。

北条泰時と北条時房が初代探題に選ばれた理由
初代六波羅探題の北方長官に任命された北条泰時は、北条義時の嫡男で将来の執権候補として期待されていた人物でした。泰時は承久の乱で幕府軍の総大将として活躍し、わずか1ヶ月で朝廷軍を打ち破った実績を持っていました。
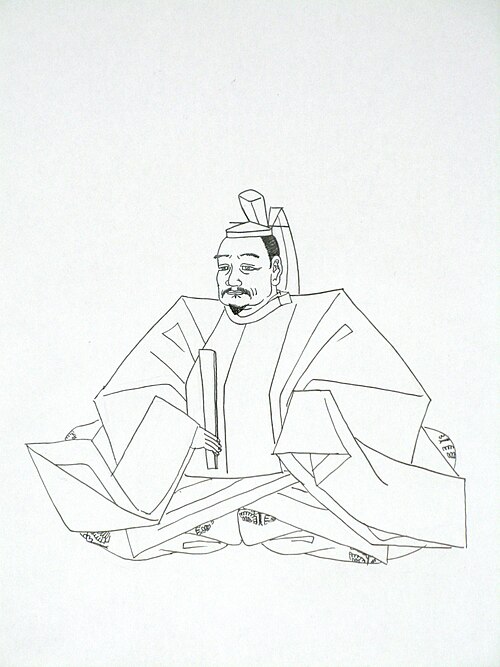
引用元「Wikipediaコモンズ」より
北条泰時は公正で実直な性格で知られ、多くの御家人から信頼されていました。戦後処理においても冷静な判断力を発揮し、後鳥羽上皇の処遇や没収した所領の分配を適切に行いました。このような能力と人望から、京都という重要拠点の責任者に最適な人物と判断されたのです。
一方、南方長官に任命された北条時房は義時の異母弟でした。時房は承久の乱で泰時とともに大軍を率いて入京し、戦場での指揮能力の高さを証明していました。泰時が政治的判断を得意とするのに対し、時房は軍事面での実務に優れていたため、両者の組み合わせは理想的なものでした。
北条泰時のその後
北条泰時は六波羅探題北方長官を約3年間務めた後、鎌倉に戻り第3代執権に就任しました。執権となった泰時は御成敗式目という武家法を制定し、公正な裁判制度を確立します。この功績により、泰時は鎌倉幕府史上最も優れた執権の一人として評価されています。
北条時房も泰時とともに鎌倉に戻り、初代連署として泰時を補佐しました。このように六波羅探題の初代長官を務めた2人は、その後も幕府の中枢で重要な役割を果たし続けました。
六波羅探題は執権・連署に次ぐ重職だった
鎌倉幕府における六波羅探題の位置づけは非常に高いものでした。幕府の役職序列において、征夷大将軍、執権、連署に次ぐ第4位とされていました。ただし4代以降の将軍は朝廷から派遣された皇族や貴族であり実権がなかったため、実質的には執権、連署に次ぐ第3の重要職と言えます。
六波羅探題の長官には北条一族の中でも特に有望視された者が任命されました。歴代の探題長官の多くが後に執権や連署に就任しており、六波羅探題は幕府内での出世コースの一つとして位置づけられていました。
六波羅探題が重職とされた理由は、その権限の大きさにありました。通常、幕府の軍を動かすには将軍や侍所長官の許可が必要でしたが、京都という遠隔地では緊急時の対応が遅れる恐れがありました。そのため六波羅探題には独断で軍を動かす権限が与えられており、これは極めて異例の措置でした。
| 役職名 | 序列 | 主な権限 |
|---|---|---|
| 征夷大将軍 | 第1位 | 幕府の最高責任者(形式的) |
| 執権 | 第2位 | 幕府の実質的な最高権力者 |
| 連署 | 第3位 | 執権の補佐役 |
| 六波羅探題 | 第4位 | 西国統治・朝廷監視・独自の軍事権 |
| 侍所長官 | 第5位 | 幕府の軍事・警察を統括 |
六波羅探題の役割と歴史的影響を理解する

| 六波羅探題の役割 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 朝廷の監視 | 後鳥羽上皇の乱の再発防止、天皇・上皇の動向把握 |
| 西国御家人の統制 | 新補地頭の管理、所領紛争の調停 |
| 裁判業務 | 西国における訴訟の審理と判決 |
| 治安維持 | 京都および西国の犯罪取り締まり |
| 軍事指揮 | 緊急時の独自判断による出兵権限 |
六波羅探題の主な役割と権限
六波羅探題の最も重要な役割は朝廷の動きを常に監視することでした。承久の乱で後鳥羽上皇が挙兵したという苦い経験から、幕府は朝廷が再び反乱を起こさないよう厳重な監視体制を敷く必要があったのです。
六波羅探題は朝廷の人事や政策決定に介入する権限を持ち、天皇の譲位や皇位継承にも影響力を行使しました。朝廷が何か重要な決定をする際には、必ず六波羅探題に相談しなければならない慣習が確立されていきます。
治安維持も六波羅探題の重要な任務でした。京都周辺での犯罪取り締まりはもちろん、寺社間の紛争や悪党と呼ばれる勢力の鎮圧なども担当しました。特に鎌倉時代後期になると、幕府や朝廷に従わない悪党の活動が活発化し、六波羅探題はその対応に追われることになります。
裁判機能の重要性
六波羅探題のもう一つの重要な役割が裁判業務でした。西国で発生した所領紛争や相続問題など、武士同士の争いを裁く権限を持っていました。これまでこうした問題は鎌倉の幕府本体で審理されていましたが、遠隔地からの訴訟には時間がかかり非効率でした。
六波羅探題が現地で裁判を行うことで、紛争解決のスピードが大幅に向上しました。また北条泰時が執権時代に制定した御成敗式目という武家法が、六波羅探題の裁判でも基準として使用されました。公正な裁判制度の確立により、西国の武士たちの幕府への信頼も高まっていきました。
西国の御家人統制と新補地頭の設置
承久の乱後、鎌倉幕府は朝廷側についた貴族の所領約3,000ヶ所を没収しました。これらの土地には新たに地頭が配置され、新補地頭と呼ばれました。新補地頭の多くは承久の乱で功績のあった東国の御家人たちでした。
新補地頭は年貢の徴収や土地の管理を任されましたが、現地の荘園領主との間でしばしば対立が生じました。領主側は元々の権利を主張し、新補地頭側は幕府の命令を根拠に支配権を主張したためです。こうした紛争を調停し解決するのも六波羅探題の重要な仕事でした。
六波羅探題は定期的に西国各地を巡回し、御家人たちの状況を把握しました。御家人が何か問題を起こせば即座に処罰し、逆に功績があれば褒賞を与えることで、幕府への忠誠心を維持させました。この統制システムにより、幕府の支配は西国にも確実に浸透していきました。
| 地頭の種類 | 設置時期 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 本補地頭 | 平家滅亡後(1185年頃) | 源頼朝の功臣が任命された地頭 |
| 新補地頭 | 承久の乱後(1221年以降) | 朝廷側の所領に新たに配置された地頭 |
御家人の軍役と動員
六波羅探題は緊急時に西国の御家人を動員する権限も持っていました。蒙古襲来の際には、九州防衛のため西国の御家人に出陣命令を出しています。このように六波羅探題は単なる監視機関ではなく、西国における幕府の軍事的拠点としても機能していました。
六波羅探題と京都所司代の違い
六波羅探題は鎌倉時代の機関ですが、後の時代にも似た役割を持つ組織が京都に置かれました。それが江戸時代の京都所司代です。両者とも朝廷の監視と京都の治安維持を目的としていましたが、いくつかの重要な違いがありました。
京都所司代の起源は織田信長が1568年に設置した京都奉行に遡ります。信長が足利義昭を奉じて入京した際、京都の統治機構として置いたのが始まりです。その後、豊臣秀吉の時代を経て、江戸幕府が京都所司代として制度化しました。
六波羅探題が北方と南方の2組織体制だったのに対し、京都所司代は単独の役職でした。また六波羅探題は西国全域の統治を担当しましたが、京都所司代の管轄は基本的に京都とその周辺に限定されていました。西国の統治は各藩の大名が担当し、京都所司代はそれらを監督する立場でした。
| 比較項目 | 六波羅探題 | 京都所司代 |
|---|---|---|
| 時代 | 鎌倉時代(1221~1333年) | 江戸時代(1600年代~1867年) |
| 設置者 | 鎌倉幕府 | 江戸幕府(起源は織田信長) |
| 組織構造 | 北方・南方の2組織 | 単独の役職 |
| 管轄範囲 | 京都および西国全域 | 主に京都とその周辺 |
| 任命者 | 北条一族 | 譜代大名 |
| 軍事権限 | 独自に出兵可能 | 幕府の承認が必要 |
六波羅探題が滅亡した経緯
1333年5月7日、六波羅探題は足利尊氏率いる軍勢の攻撃を受けて滅亡しました。約112年間にわたり京都で権勢を誇った六波羅探題の終焉は、鎌倉幕府崩壊の象徴的な出来事となりました。
六波羅探題滅亡の背景には、後醍醐天皇の倒幕運動がありました。後醍醐天皇は幕府打倒を掲げて挙兵しますが、一度は失敗して隠岐島に流されます。しかし1333年、天皇は隠岐を脱出して再び挙兵し、全国の武士に倒幕の呼びかけを行いました。
この呼びかけに応じたのが、幕府の有力御家人だった足利尊氏でした。尊氏は元々幕府軍として京都に向かっていましたが、途中で寝返りを決意します。1333年4月29日、尊氏は丹波国の篠村八幡宮で反幕府の旗印を掲げ、六波羅探題攻撃を開始しました。
最後の六波羅探題の運命
最後の北方探題は北条仲時、南方探題は北条時益でした。足利軍の攻撃に耐えきれないと判断した両探題は、光厳天皇を奉じて鎌倉へ逃れようとしました。しかし近江国の番場という場所で、追撃してきた足利軍に包囲されてしまいます。
北条仲時と時益は逃げ切れないと悟り、5月9日に番場の蓮華寺で自害しました。この時、仲時に従っていた北条一族や御家人約430名も次々と自害し、壮絶な最期を遂げました。こうして六波羅探題は完全に滅亡したのです。
足利尊氏が六波羅探題を攻めた理由
足利尊氏が六波羅探題を攻撃した理由は複雑です。尊氏は源氏の名門である足利家の当主であり、本来は幕府の有力御家人でした。しかし鎌倉幕府の北条氏による専制的な支配に不満を抱いていたのです。
鎌倉時代後期、北条氏は得宗家を中心とする一族支配を強めていきました。有力御家人たちの発言権は次第に弱まり、幕府は北条一門のための政権となっていました。足利家のような源氏の名門でさえ、重要な役職から排除されることが多くなっていたのです。
1333年、幕府は尊氏に後醍醐天皇討伐を命じました。尊氏は大軍を率いて京都に向かいますが、その途中で心変わりします。幕府への不満、後醍醐天皇の理想への共感、時代の変革への期待など、様々な思いが尊氏の決断を促しました。
尊氏の人物像と決断
足利尊氏は度量が広く無欲な性格で知られ、全国の武士たちから非常に慕われていました。敵であっても優れた人物は味方に引き入れ、部下の失敗にも寛容でした。このような人望があったからこそ、多くの武士が尊氏の決断に従って幕府を裏切ったのです。
尊氏の寝返りは単なる個人的な野心ではなく、時代の要請でもありました。鎌倉幕府の体制は限界を迎えており、新しい政治秩序が求められていました。尊氏はその歴史の転換点で、重要な役割を果たす決断をしたのです。
六波羅探題滅亡後の歴史的影響
六波羅探題の滅亡は、鎌倉幕府全体の崩壊を決定的なものにしました。京都と鎌倉という幕府の2大拠点が相次いで陥落したことで、北条氏の支配体制は完全に瓦解しました。
六波羅探題滅亡の約2週間後、鎌倉でも新田義貞率いる軍勢が幕府を攻撃し、最後の執権・北条高時は自害しました。こうして源頼朝以来約150年続いた鎌倉幕府は歴史の幕を閉じることになります。
幕府滅亡後、後醍醐天皇は建武の新政という天皇親政を開始しました。しかし公家中心の政治は武士たちの不満を招き、わずか3年で崩壊します。その後、足利尊氏が室町幕府を開き、再び武家政権の時代が訪れることになりました。
公武関係の変化
六波羅探題の存在は、朝廷と幕府の力関係を象徴していました。六波羅探題が京都に君臨していた約112年間、朝廷の権威は大きく低下し、幕府が実質的な支配者となっていました。六波羅探題の滅亡により、一時的に朝廷の権威が回復しますが、すぐに再び武家政権が確立されます。
室町幕府は六波羅探題のような京都常駐の機関を置かず、幕府自体を京都に開設しました。これにより朝廷と幕府が同じ都市に並存する体制となり、公武関係は新たな段階を迎えることになります。
よくある質問
- 六波羅探題は何年間存続したのか?
-
六波羅探題は1221年の設置から1333年の滅亡まで、約112年間存続しました。この間、鎌倉幕府の京都における重要拠点として、朝廷の監視と西国統治を担い続けました。
- 六波羅探題の北方と南方の違いは?
-
北方が上席で南方はそれに次ぐ位置づけでしたが、両者とも北条一門から任命され、協力して任務にあたりました。北方は主に政治的判断と幕府本体との連携を担当し、南方は現地の実務や軍事面を担当する傾向がありました。
- 六波羅探題の跡地は現在どこにあるのか?
-
京都市東山区の松原通から五条・七条にかけての一帯に六波羅探題はありました。現在は六波羅探題府跡の石碑が建てられており、近くの東福寺には六波羅門という関連史跡も残されています。
- 探題という名称の由来は?
-
探題という言葉は元来、仏教の論議で論題を定める役を意味していました。それが転じて政務を裁決する役職名となり、鎌倉時代末期から使われるようになりました。実際には鎌倉時代には単に六波羅と呼ばれており、六波羅探題という呼称が定着したのは室町時代以降とされています。
- 六波羅探題の長官になれるのは北条氏だけだったのか?
-
六波羅探題の長官職は北条一族がほぼ独占していました。執権・連署に次ぐ重要職であり、独自に軍を動かせる強大な権限を持っていたため、幕府の最高権力者である北条氏が一族から信頼できる人物を任命していました。
- 承久の乱がなければ六波羅探題は設置されなかったのか?
-
承久の乱は六波羅探題設置の直接的なきっかけとなりました。この事件により朝廷が幕府に武力で対抗する可能性が現実のものとなったため、幕府は京都での常設監視機関の必要性を強く認識しました。承久の乱がなければ、京都守護が存続していた可能性が高いと考えられます。
六波羅探題についてのまとめ
- 六波羅探題を設置したのは鎌倉幕府第2代執権の北条義時で承久の乱の直後である1221年に置かれた
- 承久の乱で後鳥羽上皇が幕府に反乱を起こしたことが六波羅探題設置の直接的なきっかけとなった
- 初代の北方長官には北条泰時、南方長官には北条時房が任命され北条一門の有力者が京都に駐留した
- 六波羅という場所はかつて平家一門の屋敷があった地域で京都御所に近く朝廷監視に最適な立地だった
- 京都守護は承久の乱で朝廷側に寝返ったため廃止され六波羅探題がより強化された組織として誕生した
- 六波羅探題は執権・連署に次ぐ幕府第3の重要職とされ歴代長官の多くが後に執権や連署に就任した
- 主な役割は朝廷の監視、西国御家人の統制、裁判業務、治安維持、軍事指揮など多岐にわたった
- 承久の乱後に設置された新補地頭の管理と所領紛争の調停も六波羅探題の重要な任務だった
- 六波羅探題は独自に軍を動かす権限を持ち緊急時には幕府の承認なしで出兵できた
- 江戸時代の京都所司代も朝廷監視を目的としていたが組織構造や管轄範囲に違いがあった
- 1333年5月7日に足利尊氏の攻撃を受けて六波羅探題は滅亡し約112年の歴史に幕を閉じた
- 最後の北方探題・北条仲時と南方探題・北条時益は近江国番場で約430名の家臣とともに自害した
- 足利尊氏は元々幕府の御家人だったが北条氏の専制的支配への不満と時代変革への期待から寝返った
- 六波羅探題の滅亡は鎌倉幕府崩壊を決定的にし建武の新政を経て室町幕府へと時代が移った
- 六波羅探題が存在した約112年間は朝廷の権威が低下し幕府が実質的な支配者となった時代だった


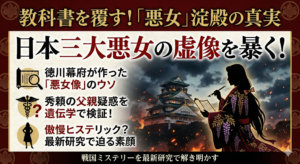
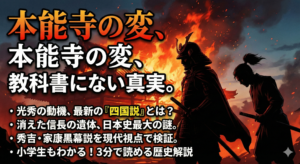
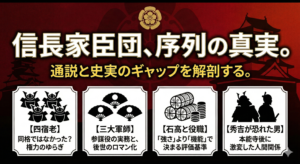
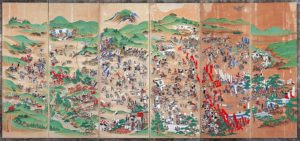
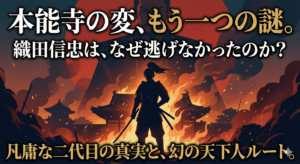
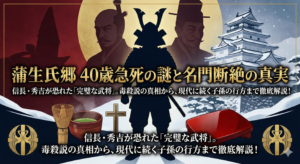

コメント