今回のテーマは徳川家康と関ヶ原の戦いです。
この記事では徳川家康と関ヶ原の戦いについて、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。
これを読めば、なぜ徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利できたのかを、カンタンに理解できます。
徳川家康が勝利できた理由は【裏切り】です。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
1,徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利できた理由は、なにか?
家康が関ヶ原の戦いで勝利できた理由は、敵将である小早川秀秋と吉川広家の両者を裏切らせて、味方に引き入れたから。
2,徳川家康は石田三成に敗北する寸前だったのか?
徳川家康に味方していた豊臣家に恩のある武将たちは、家康を裏切る可能性がとても高かった。家康が勝利するためには、短期決戦しかなかった。逆にいえば長期戦に持ち込めば、勝利できた可能性が高かった。
3,関ヶ原の戦いのその後に起こったこととは?
関ヶ原の戦いの15年後、【1615年】に大坂・夏の陣が勃発し、豊臣秀頼が自害。豊臣家は滅亡した。これにより徳川家康による天下が確固たるものとなった。ここから【1868年】の明治維新まで、【253年】にも及ぶ平和な時代が続くこととなる。
徳川家康が【関ヶ原の戦い】に勝利できた理由とは?
【1600年】、天下分け目と呼ばれた関ヶ原の戦いに徳川家康が勝利できた理由は、裏切りです。

《徳川家康》
「引用元ウィキペディアより」
家康は、石田三成がひきいた敵の武将二人を裏切らせることに成功しているのです。
その二人の武将とは、小早川秀秋と吉川広家という人物です。
特に小早川秀秋という武将を裏切らせたことは、家康の勝利を大きく決定付けた要因です。
もともと家康は、関ヶ原の戦いで、かなり不利な状態におちいっていました。
ところがその窮地を、敵から裏切り者を出させることで、一気に逆転することに成功したのです。
→→→→→【関ヶ原の戦いが起こった理由】についてくわしくはこちら
実は家康は、石田三成に敗北する寸前だった
関ヶ原の戦いで、家康は石田三成に、絶体絶命のところまで追いつめられていました。
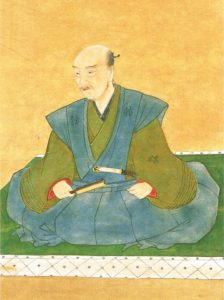
《石田三成》
「引用元ウィキペディアより」
実際に、家康が関ヶ原の戦いで石田三成に勝利できたのは、奇跡といっても良いほどです。
それほど、家康は石田三成がひきいた西軍に、崖っぷちまで追いつめられていました。
実は家康に味方していた福島正則や浅野幸長たちは、家康を裏切る可能性がとても高かったのです。
三成は豊臣家の本拠地である大坂城を占拠していました。
そしてその大坂城に住んでいたのが、豊臣秀吉の息子・豊臣秀頼です。

豊臣秀頼 京都市養源院蔵:Wikipediaよりパブリックドメイン
石田三成は、この豊臣秀頼を旗印、つまり西軍の象徴としてまつりあげていました。
福島正則や浅野幸長・山内一豊のような、豊臣家に恩がある武将たちは、秀吉の息子・秀頼に敵対することなど、絶対にできなかったのです。
家康は表向きでは、秀頼を守るために逆臣(豊臣家を乗っ取ろうとする悪い部下のこと)である石田三成を討ち果たす、という名目で石田三成がひきいた西軍と戦っていました。
しかし実際のところ、家康の目的は豊臣家を乗っ取ることでした。
実は豊臣家を守ろうとしていたのは、石田三成のほうだったのです。
これが福島正則や浅野幸長にバレると、家康は豊臣家に恩がある武将たちに、まとめて裏切られる可能性が高かったのです。
それだけではありません。
両軍の兵力は、家康の東軍よりも、石田三成がひきいた西軍の方が、圧倒的に多かったのです。
窮地におちいっていた家康が勝利するために残された選択肢は、たった一つしかありませんでした。
短期決戦です。
味方からの裏切りを回避するためにも、家康は短期決戦に打って出るしか方法が無かったのです。
実際に、家康は自分の不利を知っていたらしく、江戸へ戻り少しも動かずにいた時期があります。
おそらくこのとき家康は、西軍との和平を模索していたのでしょう。
ところが、清洲城にいた福島正則や浅野幸長らが、石田三成たちに攻撃をしかけ、岐阜城を陥落させます。
これを聞いた家康は、短期決着の可能性が出たと判断し、江戸を出撃。
関ヶ原へ敵を誘い出すことに成功します。
そして関ヶ原での短期決戦に、家康は見事に勝利したのです。
逆にいえば石田三成は、長期戦に持ち込めれば、勝利できた可能性が高かったのです。
関ヶ原の戦いのその後、いったい何が起こったのか?
関ヶ原の戦いに勝利した家康は、豊臣家を徐々に弱体化させ、最終的に滅亡させています。
【1600年】、関ヶ原の戦いで勝利した家康は、豊臣家を弱体化させることに成功します。
家康は、200万石以上あった豊臣家の領地を、65万石にまで削減し、豊臣家は没落していったのです。
関ヶ原の戦いの3年後、徳川家康は征夷大将軍に就任します。
征夷大将軍とは、武士のトップに位置する位です。
この位を手に入れた家康は、主君であった豊臣家よりも上の身分となったのです。
これ以降、家康は豊臣家に臣従を迫っていきました。つまり、主君であった豊臣家に対して、逆に【家来になれ】と迫ったわけです。
ところが豊臣家と豊臣秀頼は、家康の部下となることを、頑として受け入れなかったのです。
【1614年】、ついに豊臣家と徳川家は、大坂・冬の陣で激突することとなります。
大坂・冬の陣の翌年の【1615年】に起こった大坂・夏の陣によって、豊臣秀頼は自害しています。
これにより、豊臣家は滅亡してしまいます。
徳川家康の天下は、こうして確固たるものとなりました。
このときから、【1868年】の明治維新まで、【253年】にも渡る平和な時代が続くこととなるのです。
まとめ
本日の記事をまとめますと
1,徳川家康が関ヶ原の戦いに勝利できた理由は、なにか?
家康が関ヶ原の戦いで勝利できた理由は、敵将である小早川秀秋と吉川広家の両者を裏切らせて、味方に引き入れたから。
2,徳川家康は石田三成に敗北する寸前だったのか?
徳川家康に味方していた豊臣家に恩のある武将たちは、家康を裏切る可能性がとても高かった。家康が勝利するためには、短期決戦しかなかった。逆にいえば長期戦に持ち込めば、勝利できた可能性が高かった。
3,関ヶ原の戦いのその後に起こったこととは?
関ヶ原の戦いの15年後、【1615年】に大坂・夏の陣が勃発し、豊臣秀頼が自害。豊臣家は滅亡した。これにより徳川家康による天下が確固たるものとなった。ここから【1868年】の明治維新まで、【253年】にも及ぶ平和な時代が続くこととなる。
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。
よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました。
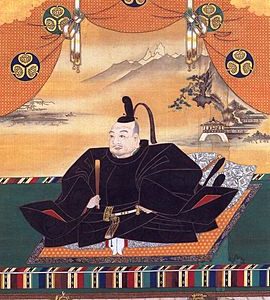
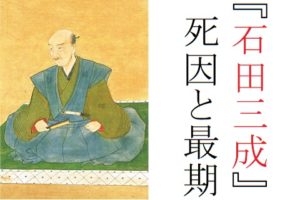

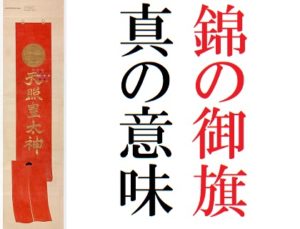





コメント