この記事では、本能寺の変のあと、織田信長の妻・濃姫こと帰蝶がどうなったのかについて、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。
これを読めば、帰蝶のその後を、カンタンに理解できます。
帰蝶は、本能寺の変のあと、30年後に亡くなっているのです。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
- 帰蝶は夫・織田信長とともに本能寺の変で戦死した、という説がある。しかしこれはあくまでも伝承であり、根拠に乏しい。おそらく帰蝶は本能寺にいなかったため、戦死していない
- 帰蝶には本能寺の変の30年後、1612年に亡くなったという説がある。帰蝶は信長より一歳年下なので、享年「78歳」となる。おそらくこれが可能性の高い説だろう
- その他にも、若くして病死した、離縁されたなどの説があるが、どれも根拠に乏しい
帰蝶(濃姫)と織田信長は、ともに本能寺の変で戦死したのか?
織田信長の正室・濃姫こと帰蝶には、夫・織田信長とともに本能寺の変で戦死したという説があります。
とはいえ、可能性はかなり低いと思います。
天正10年(1582年)6月2日、戦国の覇者・織田信長が、重臣の明智光秀に裏切られて討たれました。

《織田信長》
「引用元ウィキペディアより」
場所は、京都・本能寺
後世に本能寺の変と呼ばれた、クーデターです。
本能寺の変で信長は亡くなりました。
その直後、明智光秀は羽柴秀吉(豊臣秀吉)に山崎の戦いで敗れて戦死しています。
本能寺の変が起こったとき、織田信長の正室・濃姫こと帰蝶も、ともに戦死したという説があります。
ただ、それを裏付ける正確な資料や証拠があるわけではありません。
この説は、本能寺の変を口伝で伝える逸話にあるだけの、言ってみれば伝承でしかないのです。
当時の資料によれば、信長は本能寺にいた女性たちに対して避難命令を出しています。
信長は女性たちに対して、何度も何度も「逃げろ」と命じているとのことです。
そのため、帰蝶がたとえ本能寺にいたとしても、信長によって逃された可能性が高いのではないでしょうか。
もしも帰蝶が、明智光秀に捕まったとしても、人格者といわれている光秀が女性を虐殺した可能性は低いと思います。
しかも明智光秀と帰蝶は、一説によると【いとこ同士】なのだとか。
もし本当にいとこ同士なら、光秀が帰蝶を殺害する可能性は、さらに低いでしょう。
帰蝶は本能寺の変を生き延びたとかんがえられます。
それ以前の問題として、中国・淡路方面へ出陣する信長に帰蝶がお供をして、本能寺にいた可能性は低いと思います。
- 信長は秀吉の援軍として中国へ出陣する予定だった
- 三男・織田信孝ひきいる四国征伐軍の陣中見舞いのため、淡路に出陣する予定だった
といわれています。
明智光秀が本能寺の変を起こした動機は、諸説あります。
近年の研究によると、信長による四国征伐を止めるため、という説がもっとも有力視されています。
余談ですが、2020年放送の大河ドラマ【麒麟がくる】で、女優・川口春奈さんが帰蝶を演じておられましたが、ドラマでは帰蝶が本能寺で、信長と一緒に亡くなるシーンは描かれていませんでした。
一方、2006年放送の大河ドラマ【功名が辻】では、俳優・舘ひろしさん演じる織田信長と、女優・和久井映見さんが演じる帰蝶が登場していました。このドラマでは、帰蝶は信長と共に本能寺で亡くなる設定となっていました。
帰蝶(濃姫)が1612年まで生きていた説とは?
帰蝶は、織田信長が亡くなった30年後の1612年まで生きていたという説があります。
信長の次男・織田信雄に養われて、長生きしたというのです。
あつち殿
信長の次男・織田信雄の家族についてまとめた歴史資料【織田信雄分限帳】に【あつち殿】という名前が登場します。
【あつち殿】つまり【安土殿】という女性は、信長と関係が深い人物であると考えられているのです。
彼女は、信長の実母・土田御前よりも高い地位におかれているため、信長の正妻であった可能性が高いのです。
この安土殿が、1612年まで生きたといわれています。
安土とは、織田信長の居城・安土城のこと。
- 源頼朝を鎌倉殿
- 足利義満を室町殿
などと呼んだように、当時はその人が住んでいた本拠地の地名で呼ばれることが多かったのです。
信長にとって最重要の地である安土という名を付けられたということは、安土殿は、信長の正妻・帰蝶である可能性が高いということです。
ただ、本当に安土殿が帰蝶なのか、はっきりしていません。
安土殿=帰蝶という説が否定されることもありますが、筆者個人としては、帰蝶が信長の死後、30年生きた可能性は、高いと思います。
帰蝶が若くして病死した説とは?
帰蝶は、1567年に信長が美濃国(岐阜県南部)を制圧する以前に、病死したという説があります。
1557年、信長の側室・生駒氏が、嫡男・織田信忠を出産する以前に、帰蝶は病死したのではないか、という説があるのです。
それだけではありません。
帰蝶には、病死した説のほかにも
- 離縁された説
- 早くに亡くなっていた説
などなど。諸説あるものの、どれも信ぴょう性にとぼしいのです。
とはいえ、生駒氏が本当に信長の嫡男・織田信忠の母親なのかどうかさえ、ハッキリしていません。
それほど、当時の資料には、女性に関する記述・記録が少ないのです。
一説によると、子供がいなかった帰蝶は、生駒氏が亡くなると織田信忠を養子としたともいわれています。
信長の後継者である信忠を養子にしたということは、帰蝶が織田家でかなりの権力をもっていたことを意味しています。
本当かどうかは不明ですが、信忠を養子にしたなら、1557年の信忠誕生の以前に亡くなった説は、ありえないことになります。
やはり病死説よりも、1612年まで生きた説のほうが、可能性が高いのではないでしょうか。
本能寺の変のその後、帰蝶はどうなったのか?
あくまでも本能寺の変で帰蝶が戦死していなかったらの話ですが、織田信長が亡くなったあと、帰蝶は信長の次男・織田信雄に引き取られて生き続けたと考えられます。
先ほども説明しましたが、1587年、織田信雄の家族についてまとめた資料【織田信雄分限帳】には、しっかりと【あつち殿】と記されているのです
つまり、本能寺の変から5年後の1587年に、帰蝶は織田信雄に養われていたということになります。
信雄は、1590年に豊臣秀吉によって改易(領地没収)されています。
織田信雄は、その後1592年の朝鮮出兵のときに大名として復帰しています。
しかし、1600年の関ヶ原の戦いで、織田信雄は徳川家康によって再び改易されています。

《徳川家康》
「引用元ウィキペディアより」
1600年、関ヶ原の戦いで改易されたあと、信雄は豊臣秀頼に仕えていたと考えられています。
豊臣家は、このときすでに天下人ではなく、65万石の中堅大名になりさがっていました。
そのため、信雄の領地も、それほど大きくはなかったはずです。
- 1590~1592年
- 1600~1615年
織田信雄はこの間、改易されていたため、大名ではなかったのですから。
その1600~1615年のあいだに、安土殿は亡くなっています。
そのため、かなりわびしい生活をしていた可能性が高いです。
おそらくは出家して、織田信長の供養を続ける毎日をおくっていたのでしょう。
もしも安土殿が帰蝶であるならば、彼女は信長の1歳年下なので、享年78歳。
織田信雄はその後、1615年の大坂の陣で徳川家康の味方をして活躍しています。
その褒美に、大和国(奈良県)に5万石をもらって、子孫が今も続いています。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 帰蝶は夫・織田信長とともに本能寺の変で戦死した、という説がある。しかしこれはあくまでも伝承であり、根拠に乏しい。おそらく帰蝶は本能寺にいなかったため、戦死していない
- 帰蝶には本能寺の変の30年後、1612年に亡くなったという説がある。帰蝶は信長より一歳年下なので、享年「78歳」となる。おそらくこれが可能性の高い説だろう
- その他にも、若くして病死した、離縁されたなどの説があるが、どれも根拠に乏しい
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。
よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました。



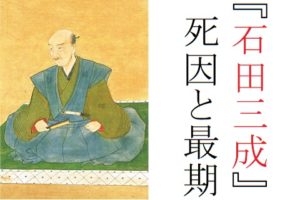

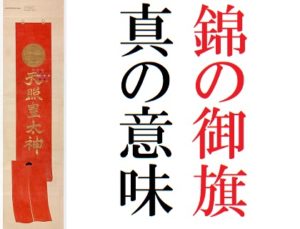





コメント