【m】
織田信長を苦しめ続けた武将・松永久秀は、日本で初めて爆死した人だと言われていますが、本当の死に様は違うのです。
私も、大学で日本史を専攻するまで詳しく知りませんでした。
松永久秀は2度信長を裏切り、壮絶な最期を遂げましたが、その子孫は現代にも続いています。
この記事では、松永久秀についてあまり詳しくない人向けに解説していきます。
これを読んで「そうだったのか、松永久秀!」とすっきりしてくださいね。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
拙者は当サイトを運営している「元・落武者」と申す者・・・。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
- 戦国時代の名将「松永久秀」には複数の子孫がいる。お笑いコンビ「爆笑問題」の「太田光」氏の妻「太田光代」さんも、松永久秀の末裔の一人
- 松永久秀がつかった家紋「蔦紋(つたもん)」は「日本十大家紋」の一つ。とても縁起の良い家紋であると言われている
- 松永久秀には数々の逸話がある。「東大寺の大仏」を焼いたとされていたり、日本初の「天守閣」を造ったり、恐妻家だったり。「爆死した」という逸話もあるが、実際には「切腹」で亡くなっている
信長を苦しめた爆死武将「松永久秀」!子孫は爆笑問題「太田光」の妻「光代」
「松永久秀」の生涯!三好家と室町幕府で重宝された教養人
「松永久秀(まつなが ひさひで)」の出自は、はっきりわかっていません。
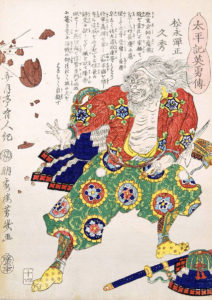
《松永久秀》
「引用元ウィキペディアより」
しかし数々の史料から、近年では「摂津(大阪府)」に生まれたと考えられています。
土豪の出身だと言われる「松永久秀」は、【1533年】か【1534年】頃に、戦国大名「三好長慶」の家臣となりました。
「三好長慶」に仕え始めた頃の松永久秀は、今でいう秘書のような仕事をしていたようです。
やがて戦にも出るようになった久秀は、部隊を任されるほどになります。三好家が出自にこだわらず、人物の特性や資質で人を登用する家柄だったのも幸いしたのでしょう。
出身がはっきりしない久秀ですが、三好家家中で出世街道を駆け上がり始めます。
【1543年】、「三好長慶」は室町幕府第13代将軍「足利義輝」と室町幕府管領「細川晴元」を京都から追放。三好政権を京都に樹立しました。
公家や京都の寺社と直接つながりを持つことになった「三好長慶」は、その交渉役に「松永久秀」を抜擢したのです。
さらに三好長慶は、松永久秀を家長に代わって家の一切を取り仕切る「家宰(かさい)」という役職につけ、娘を嫁がせました。
それだけ久秀の才能を買っていたということなのでしょう。
公家や京都の寺社と直接付き合う役職に付いた久秀は、「茶の湯(茶道)」に通じていました。
当時の「茶の湯」は茶を点てるだけではなく、茶器や掛け軸などにも詳しくなければならず、造詣が深くなるためには相当な教養が必要だったのです。
身分の低い出身だと考えられている久秀が、どこでそのような深い教養を身につけたのか、今もわかっていません。
もしかしたら三好家に仕えるようになる前に、商業都市「堺」などで身につけたのかもしれませんね。
「織田信長」の姑「斎藤道三」が油商人から一念発起して武芸を身に着けたように、いずれ役に立つと精進して「茶の湯」の技術を身に着けたのかもしれませんし、何かのきっかけで茶の湯に目覚めたのかもしれません。
いずれにせよ「三好長慶」が家宰を任せた頃には、久秀は公家や寺社との交渉役に相応しいと考えられるほどに、教養のある武将として周囲に認められていたということです。
戦でも功績を上げた久秀は、【1533年】には摂津国「滝山城(兵庫県神戸市)」の城主となりました。
さらに「三好長慶」の家臣としてだけではなく、室町幕府でも久秀は重用されるようになり、将軍「足利義輝」の御供衆(おともしゅう)の1人となったのです。(御供衆とは、将軍の側近であり最高級の名誉職)
久秀は、三好政権と室町幕府の双方で重臣として重用され、双方の交渉役として政治上にも重要な立場となりました。
【1559年】、久秀は「信貴山城(しぎさんじょう・奈良県生駒郡)」に移ります。
久秀は信貴山城を改修し、4階建ての天守閣を建築しましたが、この久秀による信貴山城の天守閣が「日本で初めて建てられた天守閣」だと言われているのです。
順風満帆に久秀が出世する一方で、主君「三好長慶」はというと信頼していた弟たちが相次いで亡くなり、更に嫡男まで亡くすという不幸に見舞われました。
精神的にショックを受けた三好長慶は、【1564年】に亡くなってしまいます。
三好家の家督は「三好長慶」の甥「義継」が継ぐことになったのですが、長慶の死の翌年【1565年】に「三好義継」は三好家の家臣(三好三人衆)とともに、とんでもない事件を起こしてしまいました。(三好三人衆とは「三好長逸(ながやす)」「三好政勝(まさかつ)」「岩成友通(いわなり ともみち)」の三名。義継の後見役)
室町幕府13代将軍「足利義輝」を襲撃し、暗殺してしまったのです。
久秀はすでに嫡男「松永久通」に家督をゆずっており、この襲撃には参加していません。
しかし久秀は「暗殺の陰謀」についてまったく知らなかったということはなく、実は首謀者ではないか・・・とも言われています。
「三好三人衆」と「三好義継」は、14代将軍に義輝のいとこ「足利義栄」をたてましたが、久秀との軋轢が生じ、畿内に混乱が生じました。
久秀は、阿波(徳島県)の三好本家を味方に取り込んだ「三好三人衆」に苦戦。一時行方をくらましてしまいます。
やがて三好三人衆は、三好家当主である「義継」まで軽んじるようになってしまい、義継はなんとか久秀を探し出して助けてくれるように頼みます。
こうして、主君の子「義継」の頼みを聞き入れた久秀は信貴山城へ帰還したのです
「織田信長」に降伏!しかしその後「信長」を裏切る
【1567年】、三好三人衆は「久秀と義継」を滅ぼすため、久秀の本拠地である大和国(奈良県)に攻め込んできました。
久秀は三好三人衆の裏をかいて奇襲をかけましたが、その時の戦闘で「東大寺大仏殿」が焼失。
何とか「東大寺の戦い」で三好三人衆に勝利したものの、「信貴山城」を敵に奪われた久秀は「多聞山城(たもんやまじょう)」へ籠もり、(ある人物)に援助を願い出ました。
三好三人衆を倒すためには、13代将軍「義輝」の弟「足利義昭」を保護する武将「織田信長」の力を利用するしかないと考えた久秀は、義継とともに信長に降伏したのです。
こうして久秀から愛用の茶器「九十九髪茄子(つくもがみなす)」を献上された信長は、畿内から「三好三人衆」を追放。義昭を15代征夷大将軍に就任させました。
信長の援軍によって大和国の支配権を取り戻した久秀は、室町幕府の幕臣でありながら、織田信長の家臣という微妙な立場になりました。
織田信長の家臣としても、浅井・朝倉攻めで窮地におちいった信長を救うなど目覚ましい活躍を果たし、信長と三好三人衆との和睦も取り持ちます。(信長最大の危機「金ヶ崎の退き口」で、松永久秀は「朽木元綱」という武将を説得して味方につけ、信長の窮地を救っている)
しかし徐々に「織田信長」と「足利義昭」の仲が悪化。信長が石山本願寺を攻め始めた頃には、2人の関係は決定的に悪化していました。
義昭は諸国の大名に「信長を討て」と命令する書状を出し、甲斐国「武田信玄」がその要請に応えます。
久秀は信長に従うふりをしながら「武田信玄」と裏で内通。【1572年】に「三好義継」や敵だった「三好三人衆」とともに、信長に反旗を翻しました。
ところが【1573年】、上洛の途中で「武田信玄」が突如として病没してしまいます。
信長との戦いに敗北した「足利義昭」は追放され、三好義継は戦死。「三好三人衆」もまた信長に敗れ、「多聞山城」に籠もった久秀はやむなく信長に降伏しました。
裏切り者ではあっても、久秀の武将としての知力・度量・技量を認めていた信長は久秀を処刑せず、大和国の領主に降格する処分のみで許します。こうして久秀の本拠地「大和国」の支配権は、久秀から信長の家臣が引き継いだのです。
松永久秀ふたたび信長を裏切るも、追いつめられて自刃
こうして信長に許されて一領主となった久秀ですが、【1577年】の石山本願寺攻めの途中、勝手に戦線を離脱。本拠地だった「信貴山城」に籠もってしまいました。久秀は再び信長を裏切ったのです。
久秀の裏切りに信長だけではなく、織田家家臣たちも「なんで?」という思いを抱き、信長は信貴山城に裏切りの理由を尋ねるため使者を送ります。ところが久秀はその使者を追い返します。
何とか穏便にことを運ぼうと思っていた信長も、使者を追い返されて激昂。息子「織田信忠」を総大将に立て、4万人の大軍で信貴山城を囲みました。
しかし久秀の立てた名城「信貴山城」を落とすのは容易ではなく、戦闘は長期化。
ところがこの時、信貴山城内に信長の内通者が発生し、信貴山城へ火がつけられました。
信長は久秀に対して
「お前が持っている茶器『古天明平蜘蛛』を差し出せば許してやる」
と提案しましたが、久秀は応じませんでした。
「平蜘蛛を鉄砲の粉(黒色火薬)で粉々にする」
と言って叩き割り、天守閣に放火。息子「松永久通」とともに自害して果てたのでした。
しかし松永家はこれで絶えてしまったのではなく、子孫は現代にまで続いています。
息子「久通」の子(久秀の孫)が博多に落ち延び、そこで質屋を営み大繁盛。
また久秀には養子「永種」がいましたが、この人も出家していたため生き延び、その息子が俳人「松永貞徳」となり活躍。
また、貞徳の子は「松永五尺」という高名な儒学者となっています。
博多に落ち延びた久秀の孫の系統の子孫には
- 陸軍中将だった「松永貞一」
- iモードの生みの親の「松永真理」
- 芸能事務所「太田プロ」社長の「太田(旧姓・松永)光代」(爆笑問題「太田光」の妻)
がいますよ。
松永久秀の家紋は「蔦紋(つたもん)」!かなり縁起の良い家紋だった
松永久秀の家紋は「蔦紋(つたもん)」です。
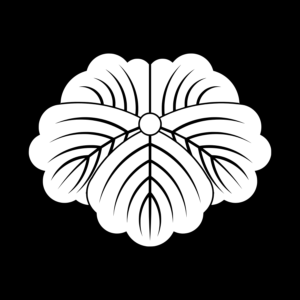
《蔦紋(つたもん)》
「引用元ウィキペディアより」
蔦紋は「日本十大家紋」の1つと言われ、非常に多く用いられている家紋でもあります。
日本十大家紋とは
- 柏紋
- 片喰紋
- 桐紋
- 鷹の羽紋
- 橘紋
- 蔦紋
- 藤紋
- 茗荷紋
- 木瓜紋
- 沢瀉紋
の10種類の家紋のことで、日本で用いられている家紋の中でも、特に数が多いもののことです。
「藤紋」は「藤原氏」の末裔が多く使っている家紋ですね。
また「柏紋」は三菱グループのロゴマークである「スリーダイヤ」の元なのです。
なぜ「柏紋」が「三菱マーク」の元となったのでしょうか。
三菱創業者「岩崎弥太郎」はもともと「土佐藩・山内家」に仕えた武士でした。その土佐藩の外部組織「海援隊」は、「後藤象二郎」によって「土佐商会」と改名。
その後「土佐商会」は「岩崎弥太郎」へと引き継がれました。
岩崎は「土佐商会」から「三菱」を立ち上げて事業を行うにあたり、主君の家であった「岩崎家」の家紋「土佐柏紋」を社のシンボルとしてつかったのです。
ちなみに海援隊は、坂本龍馬がつくった最初の株式会社「亀山社中」が土佐藩の外部機関として改名した組織です。

《土佐柏紋》
「引用元ウィキペディアより」
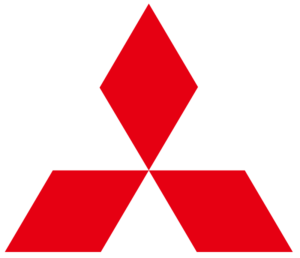
《三菱マーク》
「引用元ウィキペディアより」
皆さんの家紋にも「十大家紋」にあてはまるものがあるのでは?
こうしてみると「十大家紋」はそのほとんどが植物を由来にしていますね。
中でも「蔦」は他の樹木や建物にまつわり、どんどんとはびこっていく性質がある繁殖力が非常に強い植物です。
その生命力の強さ、繁殖力の強さは縁起が良いと考えられ、家紋に用いられるようになりました。
また漢字の成り立ちも、「草冠に鳥」と書きますから、大地に根をおろし繁殖する植物と、天空を自由に羽ばたく鳥の組み合わせも、縁起が良いと考えられた理由の1つでしょう。
武将では「松永久秀」以外にも、戦国大名「藤堂高虎」が家紋に用いています。
時代が下ると「蔦紋」は徳川一族の「松平家」でも用いられるようになりました。
葵の御紋は「徳川総本家」や「紀州・尾張・水戸」の徳川家に対して遠慮があり、「蔦紋」に変更したのかもしれません。
さらに蔦紋は他の武家だけではなく、「花柳界」の女性にも広がりました。
こうして縁起が良いとされた蔦紋は、蔦紋だけで【500種類】以上のバリエーションを持つほどに、日本中で身分を問わず幅広く使われるようになったのです。
出自のはっきりしない「松永久秀」は、家紋に縁起のいい蔦を選ぶことで、立身出世と一族の繁栄を願ったのでしょうね。
松永久秀の逸話・エピソード!東大寺を焼いたり、クリスマス停戦したり
松永久秀には、様々なエピソードがありますので、有名なものを一つ一つ見ていきましょう。
室町幕府13代将軍「足利義輝」を暗殺した?
「蘇我馬子」は日本で初めて天皇を暗殺した人物と言われていますが、「松永久秀」は室町幕府将軍「足利義輝」を暗殺した人物として知られています。
しかし隠居して息子「久通」に家督を譲っていた久秀は、事件の当時は大和国におり、この暗殺事件に参加していません。
義輝暗殺を実行したのは、「三好長慶」の子「義継」と「三好三人衆」でした。
暗殺について久秀が全く知らなかったというのは考えにくく、首謀者だったのではないか・・・・と言われていますが、どうでしょう?
これについての筆者の考えは、後述します。
「東大寺大仏殿」に放火した
さて、畿内の政情不安の中、「久秀」と「三好三人衆」との戦いが激化。その最中に「東大寺大仏殿」が焼け落ちてしまいました。
この出来事は
- 「久秀が火をつけた」
- 「三好三人衆が火をつけた」
- 「戦に参加していたキリシタンが火をつけた」
などなど様々に言われており、誰が火をつけたのかはっきりしていません。
戦乱の中で、誰かが放った火矢が運悪く大仏殿に延焼したのかもしれません。
平清盛の5男「平重衡」も東大寺に放火した・・・と言われていますが、これは重衡による放火戦術が、予想以上に拡大してしまったためだと考えられています。
クリスマスであることを理由に、敵に休戦を申し出た
【1565年】か【1566年】頃、久秀が三好三人衆との戦闘の中で
「クリスマスだから休戦しよう」
と提案したという逸話があります。
しかし実際に休戦を命じた史料は残っていません。
この逸話の元となったのは宣教師「ルイス・フロイス」の著書『日本史』ですが、該当する記述を読むと、このようになっています。
『堺の街に敵対する軍勢がいたが、堺の街で行われたクリスマスのミサに、敵対する軍勢から武士が出席した。ミサ後には仲良くパーティーに参加した。』
この記述を信じるならば、久秀側と三好三人衆側の武士が、クリスマスのミサでばったり会った・・・。しかし互いに争うことなく静かにミサに加わり、ミサの後にはクリスマス・パーティを楽しんだ・・・というだけの話ですよね。
久秀が休戦を命じたとは、どこにも書かれていないのです。
またこのクリスマス休戦は、【1566年5月】「三好三人衆」に追われた「久秀」が堺を脱出し、一時行方をくらましていた時期に当たります。
面白い話ですが「クリスマス休戦」は、史料からは確認できないエピソードなのです。
日本最初の「天守閣」をつくった
「信貴山城」を改築し、日本で最初と言われる「天守閣」を作ったのも久秀です。
久秀は「茶の湯」だけではなく、芸術全般に優れた感覚を持つ「美的センス」溢れる武将だったのでしょう。
信貴山城の天守閣は、「織田信長」が「安土城をつくる際のモデルにもなっています。
久秀は恐妻家だった?妻の亡霊に恐怖!
松永久秀には、こんな面白いエピソードがあります。
久秀が大和国の多聞山城にいた頃、「果心居士(かしんこじ)」という当時有名だった仙人を呼び出して、こう言いました。
「戦場で一度も恐怖を味わったことがないワシに、恐怖を味わわせてみよ」
と命令したのです。
果心居士は快諾し、人払いをした後に部屋の明かりを消し、自身の姿を女性の幽霊に変え、久秀に近づいていきました。
実はこの女性の幽霊は「久秀の亡妻」だったのです。
久秀は、幽霊が消えてからもしばらく震えが止まらなかったそうですよ。
その亡妻の幽霊が、主君「三好長慶」の娘だったのか、あるいは公家出身で久秀の妻となった「広橋保子」だったのかはわかりませんが、もしかしたら、久秀は恐妻家だったのかもしれませんね。
『松永久秀』について「ひとこと」言いたい!
戦国時代の武将の中では、悪役としてのイメージが強い「松永久秀」ですが、久秀は「足利義輝暗殺」を本当に首謀したのでしょうか?
私は違うのではないか・・・と思っています。
主君「三好長慶」の子「義継」が「三好三人衆」と暴走し、義輝暗殺計画を実行したそのあとで、久秀はすべてを知ったのではないでしょうか。
義輝暗殺後、「足利義栄」が14代将軍となりますが、久秀は「義栄」や「義継」「三好三人衆」と軋轢が生じたため、一時行方をくらませています。
もし義輝暗殺を久秀が首謀したのなら、暗殺後に誰か将軍に据えて世情を安定させるか・・・そこまで考え、実行に移していたはずです。
三好政権と室町幕府の交渉役でもあり、戦でも功績を上げ、出世を果たした武将「松永久通」ならば、事後の世情も予想して行動したでしょう。
しかしこの時期の久秀は、「義継」と「三好三人衆」への対応がつぎつぎと後手に回った印象があります。
おそらく久秀は「義輝暗殺」を首謀しておらず、事がおわった後にすべてを知ったのでしょう。
畿内の混乱の中で身を潜めた久秀は、「三好三人衆」に軽んじられるようになり、自身を探し出して泣きついてきた「義継」を連れて、大和国へ帰還。「織田信長」に援軍を要請しました。
「浅井・朝倉攻め」で窮地に陥った信長を救うなど、織田家家臣としても目覚ましい活躍を見せた久秀でしたが、最後には信長を裏切ります。
そのきっかけになったのは、信長が15代将軍「足利義昭」と不仲になり、追放したことでしょう。
義昭は久秀の主君「足利義輝」の弟です。
義輝の御供衆であった久秀は、義輝の弟「義昭」に対して、信長よりも親しみを抱いていたはずです。
こうして信長に反旗を翻した久秀でしたが、頼みの「武田信玄」が病没。またしても信長の軍門に下ることになりました。
しかし、心の中では鬱屈したものを抱えていたでしょう。
将軍「義昭」を追放して室町幕府を崩壊させ、大和国の支配権を奪い、よりにもよって自分と不仲である「筒井順慶」にそれを与えた信長に対して抱えていた鬱屈が、石山本願寺攻めのときに爆発。
兵を引き上げて信貴山城へ籠城する、という行動へと走らせたのです。
久秀は再三の信長の降伏勧告にも応じず、愛用の茶器を叩き割り、天守閣に放火。自害しました。
その日は奇しくも、東大寺大仏殿が三好三人衆との戦いで消失した日から、ちょうど10年目の出来事だったのです。
「日本で初めて爆死した人」と言われる久秀ですが、実は爆死していません。
茶器に火薬を詰めて爆発させる・・・・と久秀が死の間際に発言したことで、小説でそのような描写が用いられ、世間一般にそのイメージが広がってしまったのです。
実際には信貴山城落城後、久秀の首は安土城に送られ、胴体は宿敵「筒井順慶」の手によって達磨寺に埋葬されました。
健康に非常に気を使い、中風予防のために毎日頭頂部に「お灸」をすえていた久秀は、こうしてその生涯を閉じたのです。
享年、68歳(一説には70歳)でした。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 戦国時代の名将「松永久秀」には、著名人の子孫が数多くいる。お笑いコンビ「爆笑問題」の「太田光」氏の妻「太田光代」さんも、松永久秀の子孫とされている
- 松永久秀がつかった家紋「蔦紋(つたもん)」は「日本十大家紋」の一つ。松永家以外にも「蔦紋」を家紋とした家は多い。
- 松永久秀には数々の逸話がある。「東大寺の大仏」を焼いたと言われているが、真相は定かではない。また、「爆死した」という逸話もあるが、実際には爆死ではなく切腹。
この記事を短くまとめると、以下の通り
「松永久秀」の出自はよくわかっていません。
戦国大名「三好長慶」に仕えるようになり、メキメキと頭角を現し、遂には大名にまで上り詰めました。
家紋には縁起が良いと言われる「蔦紋」を用い、立身出世と一族の繁栄を願ったようです。
しかし主君「三好長慶」の死後、その嫡男「義継」が後見役「三好三人衆」とともに将軍「足利義輝」を暗殺。身の安全を図るため一時姿をくらます状況に追い込まれました。
その後「織田信長」の援軍を得て三好三人衆を京都から追放。久秀自身も織田家の家臣となり、一時期は信長とも良好な関係を築いたのです。
しかし信長が15代将軍「足利義昭」と不仲になり、久秀は信長に反旗を翻しました。
1度目は「武田信玄」の死により頓挫し、再び信長の軍門に下ります。
しかし「石山本願寺攻め」の最中、再び信長に反旗を翻した久秀は、信貴山城で壮絶な最期を遂げました。
その日は10年前に、「三好三人衆」との戦いで「東大寺大仏殿」が消失したのと同じ月・同じ日だったのです。

『達磨寺の松永久秀墓所:Wikipediaより投稿者が撮影、パブリックドメイン』
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして誠にありがとうございました。
よろしければ、また当「レキシル」へお越しくださいませ。
ありがとうございました
よろしければ以下のリンク記事も、お役立てくださいませ。
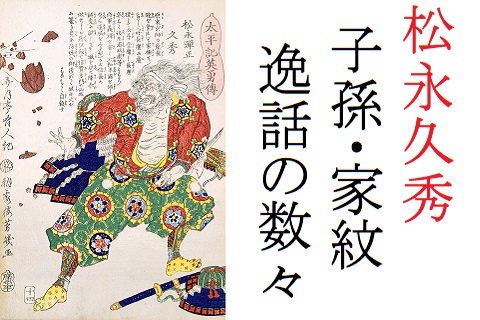



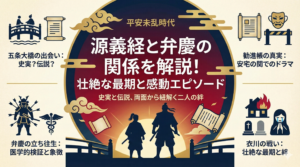


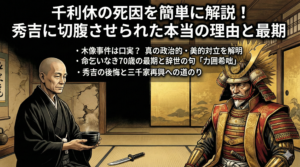
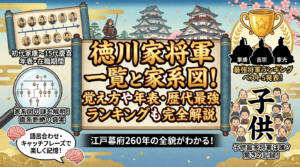
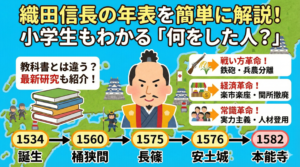
コメント