皆さんは「竹取物語の作者は紫式部という説」を、ご存知でしょうか?
この記事の内容を簡単にまとめますと以下のとおりです。
- 竹取物語の作者は、紫式部ではないという説が、一般的な説となっている
- なぜ紫式部が竹取物語の作者と噂されるかというと、源氏物語に「竹取の翁」が登場するため
- 竹取物語の作者は、源融・紀貫之・菅原道真などではないかという説がある
この記事では「竹取物語の作者」を、わかりやすく、カンタンに解説いたしました。
今は「竹取物語の作者」について、漠然としか知らなかったとしても、大丈夫です。
これを読めば、誰かに説明できるほど、「竹取物語の作者」に詳しくなれます。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
「竹取物語」と紫式部の関連性を探る6つのポイント
日本文学の中でも重要な位置を占める「竹取物語」と紫式部の作品には、多くの関連点が見られます。
これらの作品を通じて、古代から平安時代にかけての文学の流れを探ります。
「竹取物語」と紫式部の関連性については、以下の6つのポイントで詳しく解説していきます。
- 竹取物語の作者は、紫式部なのか?
- 両作品のテーマを比較する
- 文体と表現方法の違いを分析する
- 登場人物の特徴と役割を調べる
- 文学的背景と時代状況を考察する
- 各作品における女性の描写を評価する
それぞれのポイントに沿って、具体的に見ていきましょう。
竹取物語の作者は、紫式部ではない?
竹取物語の作者は、紫式部であるという説もありますが、現在では紫式部ではないという説が有力です。
実は竹取物語の作者が何者なのかは、今でも不明で、謎のままなのです。

紫式部
引用元Wikipediaより
なぜ紫式部が竹取物語の作者ではないかと噂されているかというと、彼女の作品である「源氏物語」の中に、「竹取の翁」という言葉が登場するからでしょう。(つまり紫式部が生きた平安時代中期・10世紀末から11世紀初めには、竹取物語はすでに存在していたということ)
他にもあります。
竹取物語の作者にみられる特徴は、以下の通りです。
- 和歌に非常に優れていること
- 当時は高級品だった紙を手にいれることが出来た身分であること
- 識字率つまり読み書きできる人間が少ない時代に、高度な文章を書くことが出来たこと
これらの特徴に、紫式部はぴったりと一致します。
かぐや姫が帝や貴族たちに求婚されても、それをことごとく断り、最後には月へ帰ってしまうストーリーは、まるで権力者をあざわらっているようです。
そのことから作者は、この竹取物語が完成したであろう時代に権力を握っていた藤原氏に縁のある人間ではない、と考えられています。
紫式部は、藤原為時の娘であり、藤原氏の一員です。
そのため、藤原氏をあざわらうような物語を書く可能性は低いでしょう。
さらに、この物語の作者は男性ではないかといわれています。
竹取物語の作者ではないかと言われている候補者には
- 源氏物語の主人公・光源氏のモデルといわれている源融
- 土佐日記を記した歌人・紀貫之
- 天神様として知られる学問の神・菅原道真
などがあげられています。

菅原道真
引用元Wikipediaより
次に、源氏物語と竹取物語の特徴を見ていきましょう。
両作品のテーマを比較する
「竹取物語」と紫式部の作品「源氏物語」では、テーマに明確な共通点が見られます。
例えば、どちらの作品にも美しさや愛、権力に対する人々の態度が描かれています。
特に両作品とも、主人公の「かぐや姫」と「光源氏」ともに、「美しい人物」という特徴があります。
実際に、両作品を読み進めることで、当時の社会がどのような価値観を持っていたかが窺えます。
- 両作品における愛の表現(竹取の翁・帝・貴族のかぐや姫への愛)
- 美しさに対する人々の価値観
- 権力と富への人々の姿勢
これらのテーマは、古代日本の文学において非常に重要な役割を果たしています。
さらに、これらのテーマを通じて人々の生活や思想を理解する手がかりとなります。
文体と表現方法の違いを分析する
「竹取物語」と紫式部の作品「源氏物語」には、文体に違いがあります。
「竹取物語」は日本最古の物語とされ、その語り口は比較的単純明快です。
一方、「源氏物語」は、平安時代の貴族社会を背景にした複雑な心理描写が特徴です。
- 「竹取物語」の直接的で平易な文体
- 「源氏物語」の繊細かつ複雑な心理描写
これらの文体の違いは、時代背景や作者の文学的意図に深く影響されています。
また、文体を分析することで、それぞれの作品が持つ文学的な価値や影響をより深く理解することができます。
登場人物の特徴と役割を調べる
次に、両作品に登場するキャラクターの特徴と役割に注目します。
「竹取物語」のかぐや姫や、紫式部の「源氏物語」における光源氏など、それぞれのキャラクターが持つ象徴性や役割は非常に似ています。
- かぐや姫の神秘性とその影響
- 光源氏の理想化された美男子像
つまりは、女性の理想像であるかぐや姫と、男性の理想像である光源氏という、人が理想とする人間を形にしたものが、それぞれの物語の主人公なのです。
これらのキャラクターは、日本の文学史上、非常に影響力のある存在となっています。
また、これらのキャラクターを通じて、作者が何を伝えたいのか、また、その時代の人々にどのようなメッセージがあったのかが考察できます。
文学的背景と時代状況を考察する
「竹取物語」と「源氏物語」を理解する上で、文学的背景と時代状況の理解は欠かせません。
これらの作品が成立した背景には、それぞれの時代特有の社会状況や文化が深く関わっています。
- 古代日本の神話と伝説の影響
- 平安時代の貴族社会の様子
これらの時代状況を理解することで、なぜこれらの作品が今日に至るまで読み継がれているのか、その理由が明らかになります。
各作品における女性の描写を評価する
最後に、両作品における女性の描写に焦点を当てます。
「竹取物語」のかぐや姫や、「源氏物語」の桐壺そして藤壺や紫の上など、それぞれの作品に登場する女性たちは、それぞれ異なる女性像を提示しています。
- かぐや姫の美しさとその運命
- 桐壺や藤壺や紫の上などの複雑な人間関係
これらの描写からは、当時の女性の立場や社会的制約、美の理念などが読み取れます。
また、これらの女性キャラクターを通じて、作者がどのような女性像を提示したかったのかが理解できるでしょう。
竹取物語の成立年代と作者不明の謎に迫る3つの手掛かり
「竹取物語」は、日本最古の物語文学とされ、その成立年代や作者については今なお多くの謎に包まれています。
これらの謎を解明するための手掛かりは以下の4つです。
- 古文書と写本の研究をする
- 他の同時代作品との関連を探る
- 学界の主要な仮説を検討する
それぞれの手掛かりを詳しく解説していきます。
古文書と写本の研究をする
「竹取物語」の写本は、南北朝時代の天皇である後光厳天皇によるとされる写本がもっとも古いものといわれています。
後光厳天皇は、1354〜1371年のあいだに、天皇の位についておられた天皇です。
この後光厳天皇が生まれた時代は、ちょうど室町幕府の初代将軍・足利尊氏が活躍していた時代です。

足利尊氏
引用元ウィキペディアより
ところが、後光厳天皇の写本よりも古いとされる代物は、現存はしていないものの、存在していなかったわけではありません。
もしかすると、存在していたかもしれないのです。
そのため、少なくとも竹取物語は、南北朝時代より以前に成立していた物語だということになります。(紫式部の作品に、竹取物語の「竹取の翁」が登場するので、平安時代中期以前という説が有力)
「竹取物語」の古文書や写本の研究は、作品の成立年代を明らかにする上で非常に重要です。
これらの文献は、作品がどのように伝えられ、どのような変遷を遂げてきたかを示す証拠となります。
- 現存する最古の写本の分析
- 文書の書体や用語の時代特性の調査
これらの分析から、作品が成立したおおよその時期を特定する手がかりが得られることがあります。
他の同時代作品との関連を探る
「竹取物語」が成立した時代の他の文学作品との比較は、作品の文学的な位置づけや影響を探る上で有効です。
同時期の作品とのテーマやスタイルの比較から、竹取物語独自の特徴や影響を受けた可能性がある要素を見つけることができます。
- 同時代の作品との内容比較
- スタイルやテーマでの類似点と相違点
これにより、「竹取物語」が独自の作品である理由や、他の作品に与えた影響を考えることができます。
竹取物語は源氏物語の中に、その登場人物である「竹取の翁」という言葉が登場することから、関係性が見出せます。
源氏物語の作者・紫式部は、竹取物語
学界の主要な仮説を検討する
最後に、学界で提唱されている「竹取物語」の成立年代や作者に関する主要な仮説を検討します。
これらの仮説は、古文書の解析や文学的な分析に基づいており、作品に新たな見解を提供することが多いです。
- 成立年代を巡る諸説
- 作者についての様々な推測
これらの仮説を理解し、それぞれの根拠となる証拠や考え方を詳しく見ていくことで、作品の謎に迫ることができます。
仮説としては、作者は源融・紀貫之・菅原道真などではないかという説があります。
源融は、光源氏のモデルとされた人物で、京都・嵐山には、源融の山荘があったという地に、清涼寺というお寺が残っています。
余談ながら清涼寺には、寺の修復を助けた豊臣秀頼の遺骨が大阪城から発掘され、埋葬されています。
以上の4つの手掛かりを通じて、「竹取物語」の成立年代と作者の謎に光を当ててみましょう。
竹取物語と源氏物語の比較分析4ステップ
日本文学の中でも特に有名な「竹取物語」と「源氏物語」は、異なる時代背景を持ち、それぞれ独自の特徴があります。
これらの作品を比較することで、日本の物語文学の発展を深く理解することができます。
以下の4つのステップで、両作品の違いと類似点を探っていきます。
- プロットと構造の違いを検討する
- 主題とモチーフの比較を行う
- 文学的影響と受容の歴史を調査する
- 作者の文学的意図とメッセージを推測する
それでは、各ステップに沿って解析していきましょう。
プロットと構造の違いを検討する
「竹取物語」と「源氏物語」は、その構造に顕著な違いがあります。
「竹取物語」は、かぐや姫の誕生から成長、そして月への帰還という比較的シンプルなストーリーラインです。
一方で、「源氏物語」は、光源氏の生涯を通じて多くの人物が絡む複雑な人間関係と心理描写が展開されます。
- 「竹取物語」の直線的な物語構造
- 「源氏物語」の多層的かつ複雑
これらの構造的な違いは、物語のテーマや描かれ方に大きな影響を与えています。
主題とモチーフの比較を行う
次に、両作品の主題とモチーフを比較します。
「竹取物語」の主なテーマは、美と愛、そして移り変わる運命です。
かぐや姫の美しさは多くの貴族を引き寄せますが、彼女の心は常に遠い月にありました。
対して、「源氏物語」は、愛と憎しみ、成功と挫折など、人間の複雑な感情を深く掘り下げる作品です。
光源氏の恋愛を中心に、権力や地位といった社会的なテーマも扱われています。
光源氏は、母親の桐壺と瓜二つの女性である藤壺に恋をすることからストーリーが始まります。
藤壺とのあいだに子供を儲けた光源氏ですが、藤壺との別れを経験します。
その後、光源氏はひたすらに、藤壺の面影を持つ女性を求めるのです。
つまり光源氏は、母親の面影を求めて、女性との関係を繰り返す、それが源氏物語です。
- 「竹取物語」の神秘的で哲学的なモチーフ
- 「源氏物語」の社会的かつ心理的なテーマ
これらの違いは、作品が持つ独自の世界観や読者に与える影響の深さを示しています。
文学的影響と受容の歴史を調査する
「竹取物語」と「源氏物語」は、それぞれ異なる時代に書かれたため、後世の文学に与えた影響も異なります。
「竹取物語」は物語文学の原型とも言え、多くの後世の作品に影響を与えました。
「源氏物語」は、日本文学だけでなく、世界文学においても高く評価される作品であり、多くの研究が行われています。
- 「竹取物語」の神話的・民話的要素の影響
- 「源氏物語」の心理描写がもたらす文学的影響
これらの作品が文学史に与えた影響を理解することで、日本文学の発展をさらに深く知ることができます。
作者の文学的意図とメッセージを推測する
最後に、それぞれの作品を通じて、作者が伝えたかったメッセージや文学的意図を考察します。
「竹取物語」の作者は、かぐや姫の美しさとその悲しい運命を通じて、何を読者に伝えたかったのでしょうか。
月と地上の世界との間の哲学的な隔たりは何を象徴しているのでしょうか。
それはおそらく、天皇や藤原氏という、この竹取物語が誕生した時代の絶対権力者すらも勝てない、圧倒的な存在を表現したかったのでしょう。
つまり、作者は権力の反対派、反体制派の人間だったと考えられます。
一方、「源氏物語」の紫式部は、光源氏の生涯を描くことで、どのような人間ドラマを展開させたかったのでしょうか。
社会的地位や恋愛、家族関係における人間の苦悩を深く掘り下げた意図は何だったのでしょうか。
紫式部は、源氏物語を描くことで、自らの主人である藤原道長と、その娘で一条天皇の中宮・彰子を手助けすることが目的だったといわれています。
つまり源氏物語という興味深い物語を次々と描いて、彰子へ送ることにより、一条天皇の関心を得ようとしたのです。
どういうことかというと、道長は彰子に一条天皇の子供を産ませ、その子を次の天皇に即位させて、後見人として権力を独占することが目的でした。

藤原道長
引用元Wikipediaより
そのためには、一条天皇に彰子のもとへ通ってもらう必要があったのですが、彰子のもとにベストセラー小説「源氏物語」が毎週届いていたわけです。
一条天皇は、この「源氏物語」を読みたいがために、彰子のもとへ通い、後一条天皇と後朱雀天皇という二人の後継者を残したのでした。
また、源氏物語は紫式部による藤原道長へのメッセージだったという憶測もされていますが、その真相は今も不明です。
- 「竹取物語」の月への帰還の象徴性
- 「源氏物語」の光源氏の人生の象徴性
これらの作品に込められたメッセージを考察することで、それぞれの作者の文学的な意図が見えてきます。
日本古典文学における匿名作者の歴史的意義5つ
日本の古典文学における匿名作者は、作品そのものと同じくらい興味深い存在です。
匿名性は作品の解釈や受容に大きな影響を及ぼし、その背後にある理由や影響を探ることは、文学研究において重要なポイントとなります。ここでは、匿名作者の歴史的意義を5つの視点から探ります。
- 匿名性が文学作品に与える影響を評価する
- 匿名作者の作品が歴史にどう影響したかを探る
- 文学の発展における匿名性の役割を分析する
- 作者の匿名性が読者や評価に与える影響を検討する
- 匿名作者作品の現代文学における意義を探る
それでは、これらの点について詳しく見ていきましょう。
匿名性が文学作品に与える影響を評価する
匿名性は作品の解釈において、読者が作者の意図や背景に影響されることなく、テキストそのものに集中できる環境を提供します。
これにより、作品が持つ普遍性や象徴性が強調され、多様な解釈が可能になります。
- 作品のテキスト中心の評価
- 解釈の多様性の促進
このように、作者の匿名性は作品を時間や作者の個人的背景から切り離し、文学作品としての純粋な価値を追求させます。
匿名作者の作品が歴史にどう影響したかを探る
多くの重要な文学作品が匿名で伝えられたことは、それらが社会や文化に与えた影響を考える上で見過ごせません。
特に、社会的なタブーや政治的な問題を扱う作品では、匿名性が作者を保護し、より自由な表現を可能にしました。
- 社会的・政治的な影響
- 文学的表現の自由度の拡大
匿名であることによって、時には革新的または反逆的な内容が含まれることもあります。
文学の発展における匿名性の役割を分析する
匿名性は文学のジャンルやスタイルの発展に寄与しました。
作者が明らかでないことは、新しい形式やアイデアを試す機会を与え、後の作家たちに多大な影響を与えることがあります。
- ジャンルの革新
- スタイルの多様化
匿名の状態で発表された作品が、後世の作家や流派に与えた影響は計り知れません。
作者の匿名性が読者や評価に与える影響を検討する
匿名性は読者の作品に対する期待や受け止め方にも影響します。
作者の社会的身分や性別、人種などの先入観がないため、作品自体の内容と質が直接的に評価されることになります。
- 読者の先入観の除去
- 純粋な作品評価の促進
この点で、匿名性は作品が公正に評価されるための平等な基盤を提供すると言えるでしょう。
匿名作者作品の現代文学における意義を探る
現代文学においても、匿名で発表される作品は存在感を示しています。
これらの作品は、作者のアイデンティティを超えた普遍的なテーマや問題を提起することが多く、読者にとって新たな視点を提供します。
- 普遍的なテーマの探求
- 新たな文学的視点の提供
匿名作者の作品は、文学が社会や文化にどのように働きかけるかを示す貴重な事例として、現代文学においても重要な役割を果たしています。
竹取物語のストーリーのテーマと象徴性を解析する3つの視点
「竹取物語」は日本の古典文学の中でも特に魅力的な作品であり、そのストーリーラインには深いテーマと象徴性が織り込まれています。
ここでは
- 主要な象徴としての月
- 自然と超自然の交錯
- 人間関係の象徴性
の3つの視点から解析を行います。
主要な象徴としての月とその意味を探る
「竹取物語」における最も顕著な象徴は月です。
月はかぐや姫の出自と運命を象徴しており、彼女の神秘的な美しさと孤独を表しています。
また、月は彼女が最終的に帰るべき場所として描かれ、地上の生活の一時性と比較されます。
- 月の美しさと遠さ
- 地上の世界との対比
- かぐや姫の孤独と異質性
月が象徴するのは、この世のものではない美と悲哀です。
かぐや姫の生活が地上で一時的なものであること、そして彼女が経験する精神的な断絶が、月の象徴を通じて強調されます。
竹取物語に見られる自然と超自然の交錯を分析する
物語における自然と超自然の要素の交錯は、「竹取物語」のもう一つの重要なテーマです。
竹から生まれたかぐや姫の存在自体が自然と超自然の境界を曖昧にしています。
これは、自然界の神秘と人間界の日常とが密接に結びついていることを示しています。
- 自然界からの異質な存在の出現
- 竹取老人によるかぐや姫の発見と育成
- かぐや姫の超自然的な能力と運命
物語全体を通じて、自然界と超自然界の間の相互作用が描かれ、この交錯が物語に神秘的で時には不思議な要素を加えています。
物語における人間関係とその象徴性を考察する
「竹取物語」において、人間関係はさまざまな象徴的意味を持ちます。
かぐや姫と五人の貴族たちとの関係は、地位や財産、美の追求がどのように空虚なものであるかを示しています。
彼らが提出する課題(かぐや姫の無理難題)は、物質的なものへの執着がもたらす失敗と虚しさを象徴しています。
- 求婚者たちの挑戦と失敗
- 竹取老人とかぐや姫との家族的絆
- かぐや姫の真の帰属意識の欠如
これらの人間関係を通じて、物語は愛や家族、社会的な地位に関する深い問いを投げかけています。
かぐや姫と周囲の人々との間に生じる感情のずれや誤解は、彼女の孤独と疎外感を際立たせ、最終的に彼女が地上を離れる運命を象徴的に強調します。
以上の視点から「竹取物語」のテーマと象徴性を掘り下げることで、この古典作品が持つ多層的な意味を理解することができます。
まとめ
本日の記事をまとめますと
- 竹取物語の作者は、紫式部ではないという説が、最近の研究では一般的となっている
- なぜ紫式部が竹取物語の作者と噂されるかというと、源氏物語に「竹取の翁」が登場するから
- 竹取物語の作者は、源融・紀貫之・菅原道真などではないかという説がある
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。
よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました。


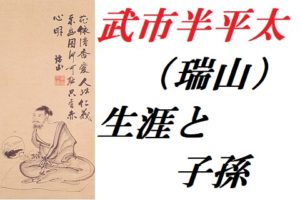
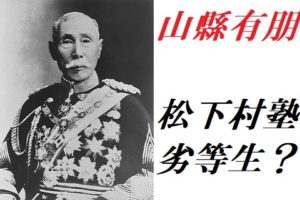
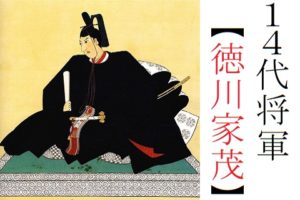

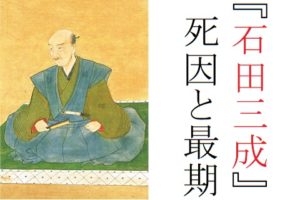

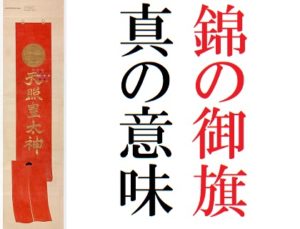

コメント