今回の主役は豊臣秀吉です。
この記事では太閤検地について、わかりやすく、短く、カンタンに解説しております。
これを読めば秀吉がおこなった太閤検地を、カンタンに理解できます。
太閤検地は、現代に例えていうならば、税金逃れを防止するためのものなのです。
歴史専門サイト「レキシル」にようこそ。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。
この記事を短く言うと
1,「閤検地とは何か?
太閤検地とは、太閤とよばれた豊臣秀吉が行なった土地の生産能力調査のこと
2,太閤検地をおこなった目的とは?
太閤検地によって、土地の生産能力と税金の集め方が統一され、全国民の税金負担が平等になった。つまり税金逃れができなくなった。
3,太閤検地は、朝鮮出兵への準備だったのか?
太閤検地によって、全国の大名たちはその支配地域の生産能力にあわせて軍役を課された。つまり太閤検地によって秀吉は、朝鮮へ何人の兵士を送り込めるのかを調査したともいえる。
太閤検地とは何か?
太閤検地とは、土地の生産力調査のことです。
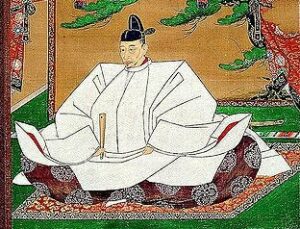
《豊臣秀吉》
「引用元ウィキペディアより」
たとえば、1m四方の土地から、一年間で何kgのお米が取れるかを調査したのです。
これにより、その土地から、どれくらいの収入が得られるのかが、正確にわかったのです。
石高制というものをご存知でしょうか?
それまでは、土地から得られる収入を貫高制といって通貨で評価していました。
例えば、〇〇m四方の土地から年間1貫(約15万円)が得られる、というように。
【1591年】の太閤検地以降は、石高制といって、米の量で評価がされるようになりました。
例えば、〇〇m四方の土地から2石(約15万円)というように。
これにより、各地の戦国大名が、年間どれくらいの収入を得ているのかが明確になりました。
それはつまり、各地の大名が、どれくらいの力(軍事力)を持っているのかが、明確になり、丸裸にされたということを意味していました。
ちなみに、なぜ豊臣秀吉が行なった検地という土地調査が、太閤検地と呼ばれているのでしょうか?
秀吉は【1591年】に、甥である豊臣秀次に関白の位をゆずり、自らは太閤と名乗りました。
太閤検地は、秀吉が太閤と名乗った頃に行われた検地であったため、秀吉が行なった検地という意味を込めて太閤検地と呼ばれるようになったのです。
ちなみに、秀吉が太閤と名乗る以前に行なった検地も、まとめて太閤検地と呼ばれることがあるようです。
→→→→→【秀吉の天下統一までの道のり】についてくわしくはこちら
太閤検地の目的をカンタン解説!平等な課税と軍役が目的だった
太閤検地の目的は、全国民への税金を、平等にすることです。
太閤検地によって、各土地の生産能力が、ハッキリしました。
ということは、その土地にいくらの税金をかければいいのかが、ハッキリしたことになるのです。
たとえば、年間30石のお米を生産する土地があったとします。
当時の豊臣秀吉が支配した日本の税金は、3分の2つまり66%が一般的でした。
つまり、この土地からは毎年20石の税金が、徴収できることになります。
当時はお米の量を計測する枡の大きさが、地方ごとにバラバラでした。
そのため
- 小さい枡をつかっている地域では、税金が少なく
- 大きい枡をつかっている地域では、税金が多い
という不平等な事態が起こっていたのです。
つまり、地方によって税金がバラバラで、地域ごとに不平等だったのです。
そのため秀吉は、枡の大きさを全国で統一して、税金の負担を、全国民で平等にしました。
しかも、土地の生産力調査も正確に行なったため、税金をゴマかすこともできなくなりました。
日本全国民への税金の負担が平等になり、ズルい税金逃れができなくなったということです。
太閤検地は、税金逃れを防止するための収入調査でもあったのです。
それだけではありません。
太閤検地によって、軍役の義務も明確になりました。
つまり、各地の土地を支配する戦国大名たちが支配する土地の大きさによって、負担する軍役の義務、つまり何人の兵士を戦争に参加させるのかという義務が、明確になったのです。
例えば、10万石の生産能力を持つ土地を支配する大名は、2500人の兵士を出兵させなくてはならない、などです。
生産能力がわかっているので、大名への軍役も、平等に負担させることが出来ます。
太閤検地によって、全国民の納税義務と、戦国大名の軍役の義務とが、明確で平等になったということです。
余談ですが、織田信長は【1582年】の最盛期に787万石もの土地を支配していました。

《織田信長》
「引用元ウィキペディアより」
クリックすると拡大できます
そこから計算される織田軍団の最大動員兵力は、最低でも約20万人程です。
太閤検地は、朝鮮出兵の準備だったのか?
太閤検地は、朝鮮出兵が行われる前年の【1591年】に行われました。
これは太閤検地が、朝鮮出兵のための準備だったことを示しています。
朝鮮出兵のとき、全国の大名たちは、その土地の生産能力にあわせて何人の兵士を朝鮮半島へ出兵させるのかという軍役を割り振られました。
たとえば独眼竜・伊達政宗は500~1500人という軍役を課されました。(政宗は約60万石という大国を支配していたが、領地が朝鮮半島から遠い奥州だったため、軍役をゆるくしてもらった)

《伊達政宗》
「引用元ウィキペディアより」
太閤検地とは、支配していた土地の生産能力を把握し、その土地の生産能力に合わせた軍役を課す、というものです。
秀吉は、太閤検地によって、何人の兵士を朝鮮半島へ送ることができるのかを計算し調査していたのでしょう。
太閤検地には、実は侵略戦争の下準備という側面もありました。
秀吉の検地は、支配する領地を広げれば広げるほどに、さらなる大軍団を集めることができるシステムとも言えるのです。
つまり、こういうことです。
秀吉は朝鮮出兵によって、朝鮮半島と明国(チャイナ)を支配していたとしたら、どうなっていたでしょう。
もしも秀吉が朝鮮半島と明国の侵略に成功していたら、朝鮮半島と明国でも、太閤検地を行なっていたでしょう。
そして、その土地の生産能力に合わせて、朝鮮・明国の各地に軍役を与えて兵士を集め、さらなる大軍団で次の土地を侵略していたと考えられます。
太閤検地は、ただの生産能力の調査ではなく、他国侵略の下準備だったともいえるのです。
まとめ
本日の記事をまとめますと
1,太閤検地とは、太閤とよばれた豊臣秀吉が行なった土地の生産能力調査のこと
2,太閤検地をおこなった目的は、土地の生産能力と税金の集め方を統一し、全国民の税金負担が平等にすること。つまり税金逃れを無くすことが目的の一つだった。
3,太閤検地によって、全国の大名たちはその支配地域の生産能力にあわせて軍役を課された。つまり太閤検地によって秀吉は、朝鮮へ何人の兵士を送り込めるのかを調査したともいえる。
以上となります。
本日は「レキシル」へお越し下さいまして、誠にありがとうございました。
よろしければ、またぜひ当サイトへお越しくださいませ。
ありがとうございました。
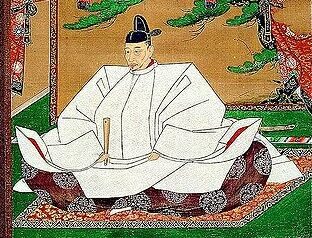
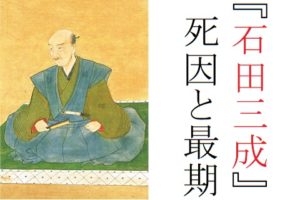

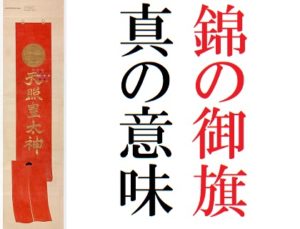





コメント